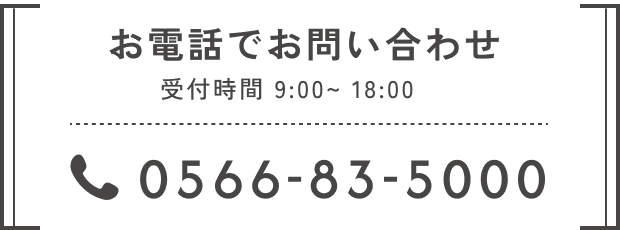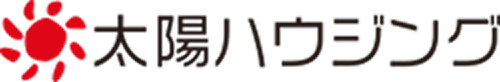BLOG
ブログ
トイレの床のほこり取り!
こんにちは、サービス課リフォーム担当の髙瀬です。
今回は、知多市のT様よりトイレリフォームのご依頼をいただきました。
T様のご依頼内容は、おうちに来て頂いた方に心地よくトイレを利用して
頂きたい。汚れが便器につきにくく掃除やお手入れしやすいトイレを
ご要望でしたので、LIXILのリフォレを提案させて頂きました。
あわせて、トイレお掃除の裏技もお伝えしました。
ほこりがたまりやすい床の、ほこりを取るのには、ウェットタイプのシートより
乾いたシートの方が効率的に取れることをご存じですか?

ほこりは水分を含むとこびりつきやすくなり、汚れが残ってしまいます。
ドライタイプのシートを使うと簡単にほこりが取れます。
シートの代わりにトイレットペーパーでもOKです!
ほこりを取った後にウェットシートで拭き取れば年末の大掃除は完璧です。
ぜひご参考ください。