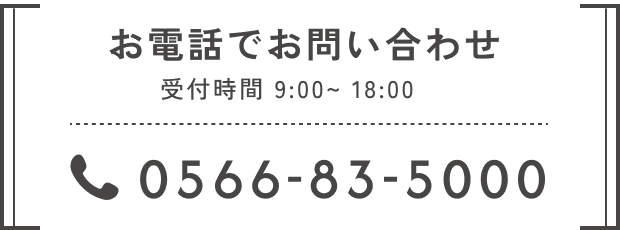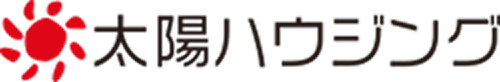COLUMN
家づくりコラム
図面を見るのが楽しくなる!知っておきたい「専門用語」とは?
こんにちは、太陽ハウジングです。
家づくりを進めていくと、「聞き慣れない言葉」が出てくることってありませんか?
打ち合わせの途中で「その言葉、初めて聞きました…」と少し不安そうにされるお客さまも少なくありません。
設計担当や現場監督、職人が日常的に使っている言葉の中には、初めて家を建てるお客さまにはピンとこない表現も多いものです。現場では当たり前でも、最初は呪文みたいに聞こえることもありますよね。
でも、ほんの少し言葉の意味を知っておくだけで、打ち合わせがぐっと楽しくなります。さらに、完成後の「えっ、家具が入らない…」「思っていたより狭かった…」といった後悔も防ぐことにもつながります。
今回のコラムは、そんな現場ならではの言葉を中心に、図面の読み方や寸法の考え方などを分かりやすく解説します。

■家具が入らない!?図面の寸法ルール
「ダイニングテーブルを置いたら通路が窮屈…」
「新居用に購入した冷蔵庫が収まらない…」
「収納内に予定していたケースが数センチ収まらない…」
実はこうしたトラブルの原因の多くは、寸法の読み方のズレなんです。
図面上では、寸法を基本的にミリ(mm)単位で表記されています。
例えば、図面に「300」と書かれていれば、30センチという意味になります。
また、この寸法にも、いくつかの種類があります。
建物の平面図では、壁の中心線を基準にした寸法が記されています。
この「壁の中心と壁の中心との距離」を「芯芯(しんしん)」と呼び、現場では
「芯芯でいくつ?」という会話がよく交わされます。
一方で、壁の内側から内側までの距離を「内法(うちのり)」、外側から外側までの距離を「外寸(がいすん)」と呼びます。
家具や家電を置くときに大切なのは、図面の寸法そのものではなく、内法で確認すること。芯芯は壁の真ん中から真ん中の寸法なので、実際に家具が入るスペース(内法)はそれよりも小さくなります。
最初はややこしく感じますが、意味がわかった瞬間に図面の線が立体的に見えはじめます。
図面の寸法を正しく読み取れると、家具の配置や動線のイメージがぐっと現実的になります。「ここにこれを置こう」と考える時間も、家づくりの楽しみのひとつ。
設計担当と「どこまでが実際に使える寸法なのか」を共有しておくと、イメージと実際の空間がずれにくくなります。

■家具の寸法を測るときに役立つ「W・D・H」
家具や家電のサイズを表すときによく使われるのが、W(幅)・D(奥行き)・H(高さ) という表記です。それぞれ、W=幅(Width)、D=奥行き(Depth)、H=高さ(Height)を意味します。
実は、この順番にもルールがあります。箱形のものは W(幅)⇒D(奥行き)⇒H(高さ)の順で書くのが基本ルール。
例えば、「300W×250D×120H」と書かれていたら、幅30cm・奥行き25cm・高さ12cmという意味になります。
冷蔵庫や洗濯機のようにWとDが近い家電は、この順番を意識しておくだけで、「あれ、どっちが奥行き?」という混乱を防げます。
これを知っているだけで、家具のすれ違い事故をぐっと減らせます。

ちなみに、図面を扱う設計担当はこの順番を体で覚えているため、W・D・Hの並びが違うと少し違和感を覚えるほど。
設計担当から家具や家電の寸法を聞かれたときは、メモを「W・D・H」の順にそろえて伝えると、収まりの精度がぐっと上がります。
■「GL」や「CH」って何?図面で見る建物の高さ
図面を見ていると、「GL」「1FL」「2FL」「CH」など、アルファベットがたくさん並んでいて、ちょっと難しそうに感じることはありませんか?
これらはすべて、建物の高さを表す記号ですが、ひとつずつ見ていくと、意外とシンプル。
GL(グランドライン):地盤の高さ(地面の基準)
1FL/2FL:1階・2階の床の高さ
RFL(ルーフフロアライン):屋根の梁の上
CH(シーリングハイト):天井の高さ
例えば「CH2400」とあれば、天井高が2.4メートルという意味です。
記号の意味がわかると、図面の中に高さのイメージが浮かび上がってきます。
■昔の日本で使われていた「尺貫法」
「1尺」「1寸」といった言葉をどこかで聞いたことはありませんか?
日本ではかつて「尺貫法(しゃっかんほう)」という単位が使われていました。
「1尺=約30.3cm」、「1寸=約3cm」、「1分=約3mm」など、今のミリ表記のもとになっている単位です。
ちなみに、「一寸法師」は、身長3cmほどの小さな男の子という意味で、単位を知ると、昔話の世界がちょっとリアルに感じられますね。
現在はミリ(mm)表記が主流ですが、古い図面や古民家の資料では今でもこの単位が登場します。
ベテランの職人さんとの会話の中でも、「一寸くらい出とるな」なんて言葉が飛び交うことがあります。こうした単位を知ることは、職人さんと同じ景色を共有し、家づくりをもっと楽しくする第一歩になるかもしれません。

■職人さんの会話からわかる、家づくりの奥深さ
図面の線と数字だけでは伝えきれないことが、家づくりの現場にはたくさんあります。
「もう少しチリを取って」
「ここは面一で合わせよう」
そんな職人さんたちの言葉には、仕上がりの美しさや住む人の心地よさを思う気持ちが込められています。
・チリ(ちり)
建具や壁などを取りつけるときに、わざと少しだけつくる「すき間」のこと。ほんの数ミリのチリがあることで、ドアの開け閉めがスムーズになったり、陰影のラインがきれいに見えたりします。
ぴったりすぎるより、ほんの少し「ゆとり」をもたせる。
それが、長く心地よく暮らすための知恵でもあります。
・面一(めんいち)・ゾロ
「ラインをそろえる」という意味で使われる言葉です。
例えば、壁と棚、窓や建具、スイッチの高さなどを面一すると、全体がすっきりと整って見えます。
図面では見えない揃いの美学を、職人さんたちは感覚で合わせています。
住む人が気づかないほど自然に、美しい空間ができていくのです。
・見込み寸法(みこみすんぽう)
壁の厚みや、部材を組み合わせたときにできるか奥行きの寸法のこと。扉や窓枠を設計するとき、この「見込み」をどう取るかで印象が大きく変わります。
例えば、窓まわりに少し見込みをとるだけで、光の入り方や影の出方がやわらかくなります。
こうした言葉のひとつひとつに、「いい家をつくりたい」という職人の思いが息づいています図面を読めなくても、その言葉の背景を知るだけで、家づくりがぐっと身近に感じられるはずです。

家づくりの言葉には、数字の奥にも“人の思い”が込められています。
図面を読むことは、家を「知る」ことだけでなく、そこに関わる人たちのやさしさや工夫を感じることでもあります。
そんな言葉の一つひとつを通して、「自分の家ができていく時間」を、より楽しんでいただけたら嬉しいです。