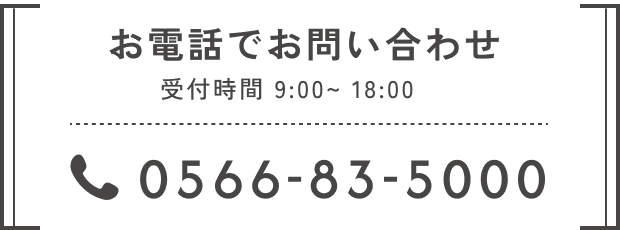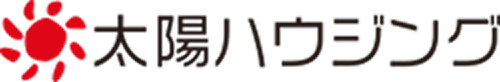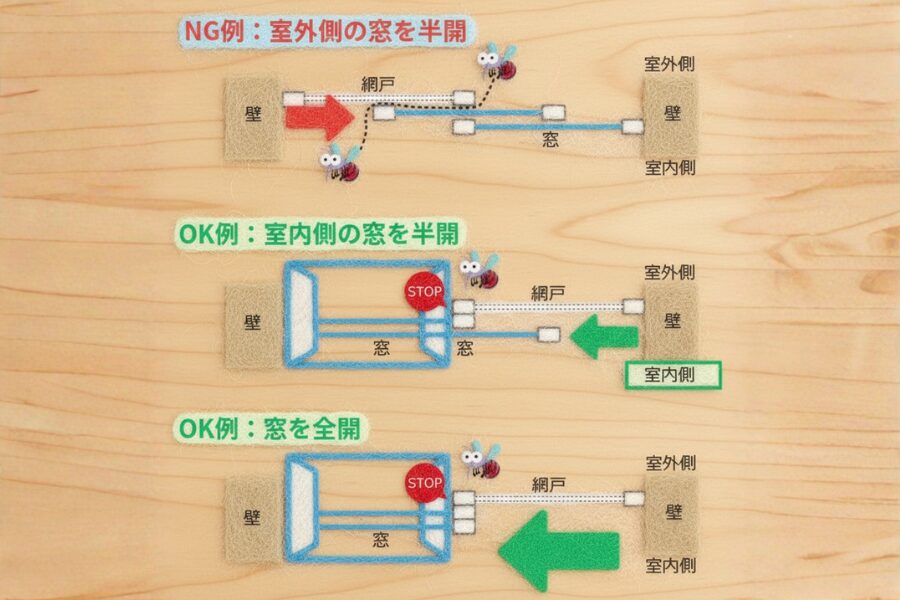COLUMN
家づくりコラム
【かっこいいデザイン住宅の落とし穴】見た目の裏にある「通気」と「雨仕舞」の大切な話
こんにちは、太陽ハウジングです。
最近、「デザイン性の高い家を建てたい」という声をよく耳にします。
SNSで見かけるおしゃれな住宅に「こんな家に住めたら…」と思う方も多いのではないでしょうか。街を歩いていて「わ、この家かっこいいな」と感じたこと、ありませんか?
少し前までは軒のない真っ白なキューブ型の家が人気でしたが、最近では、2階が少し張り出した「オーバーハングデザイン」が人気を集めています。
立体的な陰影と軽やかなフォルムが映え、SNSでは「#オーバーハングの家」「#浮いて見える家」といったタグが増えています。
でも、かっこいいなと思う反面、見た目だけで家を選ぶと、思わぬ落とし穴が潜んでいることもあります。それは見た目のデザインが美しいほど、構造は複雑になるからです。
もちろん、「かっこいい家を建ててはいけない」という話ではありません。
むしろ、デザイン性の高い住まいは心を弾ませ、暮らしを豊かにしてくれます。ただし、見えない部分にこそ“ひと工夫”が欠かせません。

そして近年は、気候の変化がはっきりしています。日本の夏はより長く、より暑く、より湿気が多くなりました。この環境下では、「通気・換気(熱と湿気を逃がす仕組み)」と、「雨仕舞(雨を受け流して建物に入れない工夫)」の良し悪しが、これまで以上に住み心地と家の寿命を左右します。
とくに、意匠性の高い屋根や外壁形状ほど、見えない部分の難易度が上がります。
そこで今回のコラムは、見た目の先にある「通気・換気」と「雨仕舞」についてお話しします。少し専門的なテーマかもしれませんが、「かっこよさを長く保つための大切な視点」として、家づくりの参考にしていただければと思います。
■デザインが複雑になるほど、空気の通り道は難しくなる
軒ゼロですっきり見せるモダン屋根。箱型のキューブに凹凸を利かせた外観。深いインナーバルコニー。ビルトインガレージ。2階を張り出すオーバーハング。平屋ベースに少しだけ2階を載せるスキップ的な構成は、いまどきの家を象徴するデザインです。
こうしたデザインの裏側では、「空気の通り道=通気の設計」がとても大切になります。
見た目はシンプルでも、家の中(特に壁や屋根の中)では、「空気をどこから入れて、どこへ抜けてさせるか」を計画的に設計しないと、湿気や熱がこもり、家の寿命を縮めてしまうことがあるのです。
・軒の出がある家と、軒ゼロの家の違い
昔ながらの三角屋根(切妻や寄棟)は、軒があることで自然な空気の流れが生まれます。壁の中を上がった空気が軒の下を通り、屋根のてっぺん(棟)から外に抜けていくので、湿気や熱がこもりにくく、自然な空気の循環ができます。
一方で軒がない家や張り出しのある構造では、この逃げ道を設計段階から工夫しなければなりません。
軒がない「軒ゼロ」のデザインは見た目がシャープな反面、この空気の出入り口をつくるのがとても難しく、吸気・排気の経路取りがシビアです。見た目はフラットでも、内部ではわずかな隙間で空気を通すため、細かい工夫と高い施工技術が必要になります。
見た目は軒がないように見せても、実際には少しだけ軒を出して通気を確保するなど、安全性を考えた設計をすることが大切です。

・キューブ住宅の落とし穴
キューブ住宅では、屋根がフラットに見えても、実際は少し落とした“くぼみ”があり、
その周りを囲うように「パラペット(立ち上がり壁)」があります。
この部分は雨水を防ぎながら空気を逃がすという、相反する2つの仕事を同時にこなさなければならないため、設計・施工の腕が問われます。
現場では、雨を止めつつ空気を抜く専用部材など、雨を防ぎながら空気を抜けるよう工夫された専用パーツを使うことが大事です。安易な施工やコスト削減によってここを簡略化すると、後で雨漏りや内部結露といったトラブルにつながることもあります。
・デザイン性の高い家ほど、見えない部分が大事
深いインナーバルコニーやビルトインガレージ、オーバーハング、スキップフロア構成のようにデザイン性の高い住宅ほど、実は内部の通気設計や防水設計の難易度が上がります。
見た目のデザインばかりに注目しがちですが、「見た目の美しさ」と「空気の通り道」を両立を考えることが、長く快適に暮らせる家をつくるためのポイントです。
・「通す(換気)」と「止める(防水)」のせめぎあい
屋根と壁が交わる部分は特に注意が必要です。屋根の熱気がたまりやすく、換気が足りないと蒸し風呂状態になることも。でも隙間を作りすぎると、今度は雨が入りやすくなります。つまり「空気を通す(換気)」と「水を止める(防水)」は綱引きの関係です。
設計の段階で、「どこから空気が入り」「どこから確実に抜けるのか」「雨水はどこで止まり、どこへ流れるのか」をしっかり考えておく必要があります。
どの面から空気が入り、どこで確実に抜けるのか。
雨水はどの段で切り、どこへ落ちるのか。
これらを点や面ではなく、空気と水の流れとして理解できているか。
そこが、デザイン住宅を長持ちさせるための分かれ道になります。
デザインの自由度が高い家ほど、見えない部分の工夫が命です。
外観の美しさに目を奪われがちですが、その裏で「家を長持ちさせる通気の仕組み」がしっかり考えられているか、ぜひチェックしてみてください。

■ 「雨仕舞」と「防水」は似て非なるもの(似ているようで実は違う)
家を雨から守る方法には、大きく分けて「雨仕舞(あまじまい)」と「防水」という2つの考え方があります。どちらも雨から家を守るという意味で目的は同じですが、実はやり方や考え方が全く違います。
・雨仕舞とは?
雨仕舞とは、雨を「入れないようにする」のではなく、「入りにくく、たまらず、自然に流れ落ちるようにする」工夫のことです。つまり、「水の流れをコントロールする」考え方です。
例えば、軒の出や水切り金物、外壁の段差・見切り、笠木の形状などが代表的な例です。
昔の日本の家は、深い軒や瓦屋根で「雨を遠ざける形」を作っていました。多少の雨が入っても、自然に外へ流れ出て乾く仕組みになっていたのです。
経年変化に強く、長期的な安心感を支える日本の気候に合った知恵と言えます。
・防水とは?
防水は、材料の力で雨を完全に止める方法で、シートや塗膜、テープ、シーリング(コーキング)などで水の通り道を塞ぐ発想です。
雨の通り道をふさぐことで、家の中に水を入れないようにします。
フラットな意匠や軒ゼロが人気のため、どうしても防水に頼る場面が増えています。ただし、防水材には「寿命」があり、時間とともに劣化します。
ほんの小さなひびや隙間ができるだけで、そこから湿気が壁の中に入り込んでしまうこともあります。
・理想は「雨仕舞」×「防水」の二段構え
雨仕舞と防水、どちらが大事というわけではありません。本当に安心できる家は、この2つをうまく組み合わせている家です。
「雨がかかりにくい形(雨仕舞)」×「もし雨が入っても中に入らない構造(防水)」
つまり、デザインの工夫+材料の力で守る二段構えの設計です。
雨仕舞で雨を逃がす工夫をしておけば、防水材が少し劣化してもすぐに問題にはなりません。逆に、防水だけに頼った家は、経年劣化によってトラブルが起きやすくなります。
見た目のデザインを優先した家ほど、「雨の逃げ道」をどうつくるかがとても大切です。
家を長持ちさせるためには、「雨を遠ざける雨仕舞」と「材料で水を止める防水」
この両方がそろっていることが大切です。
デザインの美しさの裏には、見えない雨対策がある。
それが、長く快適に暮らせる家の条件です。

■夏に起きる「夏型結露」という落とし穴
「雨も降っていないのに、壁の中が濡れている」そんな不思議なトラブルが、実は最近増えています。そんなトラブルの正体が夏型結露です。
真夏の昼間、外気温は40℃近い猛暑。屋根や外壁は太陽に焼かれて熱せられている一方で、室内はエアコンで25℃前後に冷やされています。
この外と中の温度差に、湿った空気が重なると、壁の中や天井裏など、見えない場所で結露(水滴)が発生してしまうことがあります。
屋根直下を居室にした間取り、ビルトインガレージやオーバーハングで通気が複雑化している構成、インナーバルコニーで閉じた形状など、通気が複雑な構造は特に注意。
これらの構造は空気の通り道(通気層)や換気の流れが複雑になりやすく、一部で空気が滞ると、そこに湿気が溜まって結露が起きるリスクが増します。
雨仕舞や防水ももちろん大事ですが、夏型結露のようなトラブルを防ぐには、通気と換気の計画が欠かせません。
家は、私たちの体と同じように、「呼吸をしている」と思ってください。
空気が入り、出ていく流れがあることで、湿気や熱を外へ逃がし、家の中を健やかに保っています。
外観デザインが複雑になるほど、この「空気の通り道」の設計は難しくなります。
でも、ここをおろそかにすると、せっかくの美しい家が、数年後に結露やカビで悩まされることも。
「防水で雨を止める」だけでなく、「空気を通して湿気を逃がす」
この両方を考えることが、快適で長持ちする“デザイン住宅”のカギです。
夏型結露は、見えない場所で起こる静かな雨漏りです。
エアコンの効いた快適な部屋の裏で、家が汗をかいているかもしれません。
家も人と同じで、呼吸ができなくなると、体調を崩します。見えないところで「呼吸できる家」になっているか。それが、これからの家づくりで大切にしたい視点です。
■安さの影にある、見えないリスクとは?
最近の家は、軒の出が短く、デザインがすっきりしているものが増えました。その一方で、雨を防ぐための仕組みが「防水材まかせ」になりがちです。
壁のすき間を埋めるコーキングや防水テープ。見た目はしっかり密閉されていても、これらには寿命があります。
数年、十数年のうちに少しずつ劣化し、わずかなひびや隙間から湿気が入り込むこともあるのです。
例えば、分譲住宅や建売住宅などでは、「この予算で仕上げてほしい」という条件の中で家が建てられます。もし「この予算で仕上げて」と発注されれば、どうなるか?
コストを抑えるために、目に見えない部分の手間や部材が後回しにされてしまうことがあります。
完成時はきれいに見えても、「今、雨漏りしていない」ことと、「10年後も安心して暮らせる」ことは別問題。家の本当の耐久性は、見えないところへの配慮で決まります。

■質問することは、家を守る力になる
もう一度言いますが「かっこいい家を建ててはいけない」という話ではありません。
むしろ、かっこよくて長持ちする家を一緒に考えていくために、家づくりの途中でも質問をしてみてください。質問は品質を守る力です。
「この壁の中の空気は、どこから入ってどこに抜けるんですか?」
「軒のない部分は、どうやって雨を逃がすようにしているんですか?」
「窓まわりの防水は、どんな方法でやっていますか?」
「バルコニーの排水は、詰まったときの予備も考えられていますか?」
こうした質問は、現場にプレッシャーではなく良い緊張感を与えます。
デザインか、性能か————
どちらかを選ばなければいけない時代ではありません。
これからは、「見た目の美しさ」も、「構造の確かさ」も、両立できる家づくりへ。
そして、お客さまと工務店が対話しながら進めるチームの家づくりが大切です。
太陽ハウジングは、「かっこいい」と「安心」をどちらも叶えたい方の味方です。
見た目の美しいデザインだけでなく、見えない部分まで丁寧に。
10年、20年先まで「建ててよかった」と思える住まいを、一緒に考えていきましょう。
「かっこいい家」を選ぶとき、本当に重視したいのは、そこに暮らす「その先の毎日」。
通気や雨仕舞といった設計がきちんとなされているかどうかで、住み心地は大きく変わります。
気になるデザインや間取りがあれば、まずはモデルハウスに足を運んで、実際の風通しや窓の配置、水まわりの納まりなどを体感してみてください。見た目だけではわからない、本当の住みやすさが見えてきます。
▼モデルハウスはこちら
モデルハウスを見る