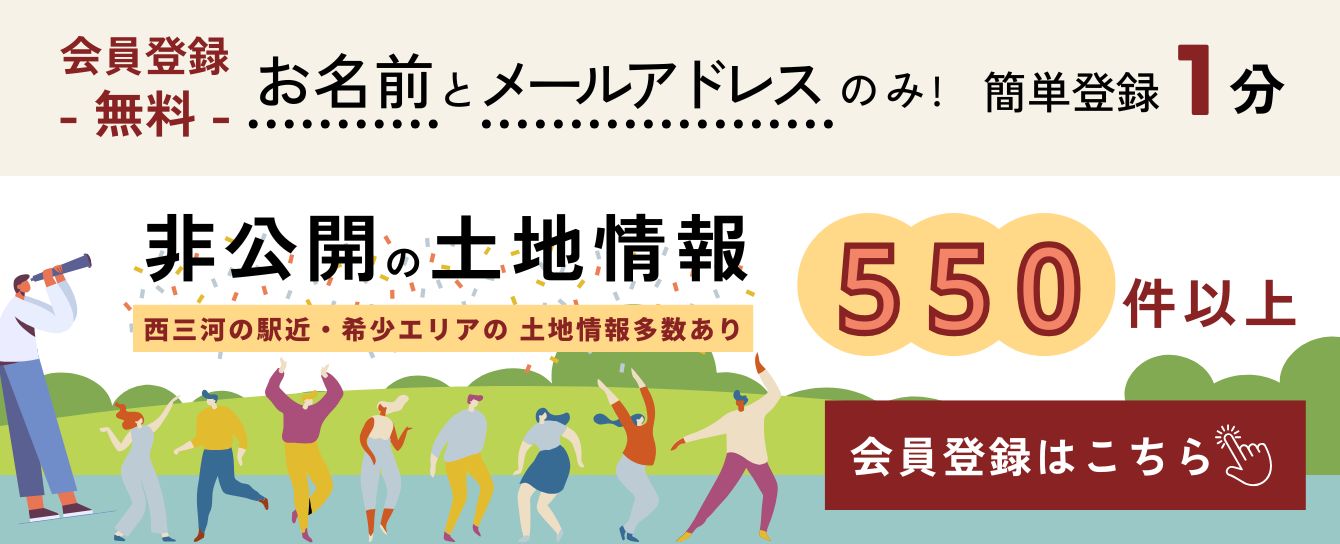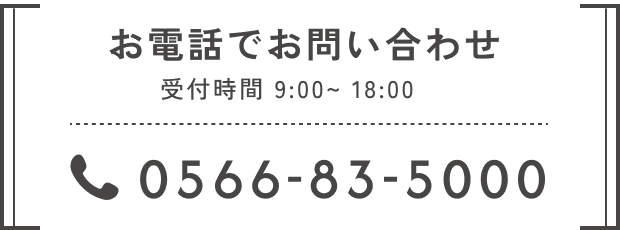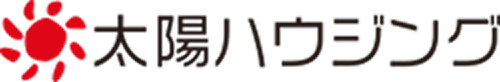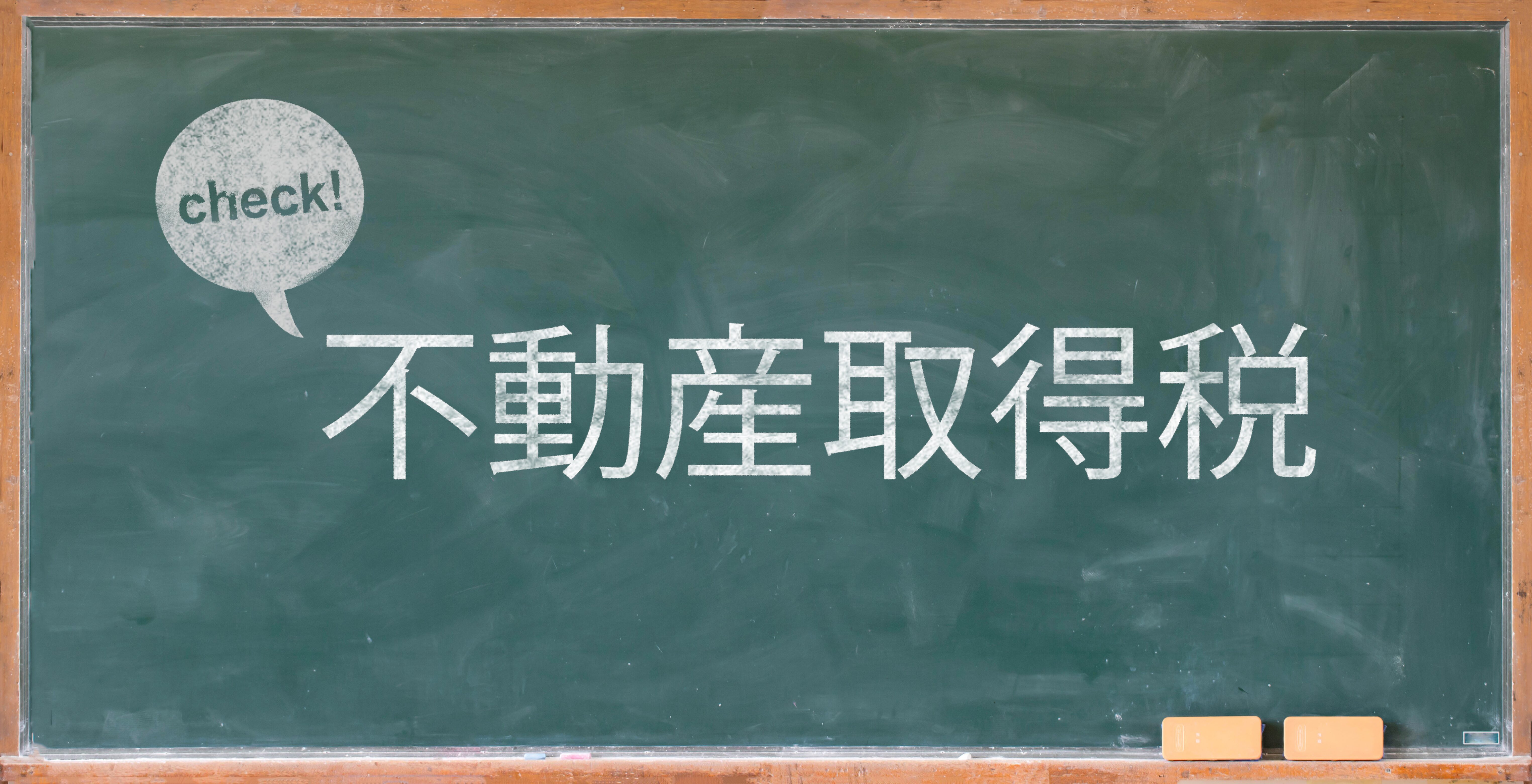COLUMN
家づくりコラム
【2025年保存版】土地・資金・広さ・年収・金利・設備までデータから読み解く注文住宅の“いま”を解説します。
こんにちは、太陽ハウジングです。
今回は、先日発表された国土交通省「住宅市場調査(令和6年度)」をもとに、注文住宅に関する最新データをまとめました。土地価格や家づくりに必要な総資金、延べ床面積の傾向、世帯年収や金利タイプ、そして宅配ボックスや太陽光発電といった最新設備の普及率までご紹介します。
「これから家づくりを考えたい」という方が相場感をつかみ、安心して判断するための視点をお届けします。

■土地価格の上昇は想像以上
令和2年度:1,545万円 → 令和6年度:2,082万円(+34.8%)
わずか4年間で全国平均の土地購入費は500万円以上アップ。都市部では「土地代が建物予算を圧迫する」とうい状況が広がっています。
全国平均で1.3倍、都市部に関しては1.5倍まで上がっています。
土地の値上がりが大きい今、「どのエリアで探すか」が家づくりの成否を左右します。場所と建物の優先順位を整理しておくことが大切です。
■家づくりに必要な総資金
・土地から購入する場合
平均:6,188万円(全国)/7,364万円(三大都市圏)
中央値:5,030万円(全国)/5,800万円(三大都市圏)
・土地を持っている場合(建物のみ)
平均:4,695万円(全国)/5,243万円(三大都市圏)
中央値:4,000万円(全国)/4,170万円(三大都市圏)
平均値は高額事例(億単位の豪華な家を建てた一部の層など)に大きく引っ張られてしまうため、実際の相場感を知るには、1番のボリュームゾーンである「中央値」を確認するのがおすすめです。
つまり、土地から購入するなら約5,000万円前後、建物だけなら約4,000万円前後が現実的な相場といえます。
ここで注目したいのが、太陽ハウジングの建物価格平均(2025年)は2,478万円という点。全国平均(建物のみ:4,695万円)より約1,500万円も低い水準です。
全国的には高額化が進む一方で、太陽ハウジングは「必要な部分にしっかり投資し、余計なコストを抑える」姿勢を貫き、価格に表れています。
結果として、賢い選択をすれば1,000万円以上の差が生まれる可能性がある。
これが家づくりの大きなポイントです。
全国の数字を眺めると「家づくりはとても高額な買い物」という感覚に圧倒されがちですが、太陽ハウジングの価格水準を知ると「地域に根差した工務店で建てる選択肢は、想像以上に堅実で安心」と感じられるかもしれません。
■延べ床面積の傾向
令和2年度:116.8㎡ → 令和6年度:113.8㎡(−2.6%)
少しずつコンパクト化が進んでいますが、「小さい=不便」ではなく、設計や収納の工夫で「小さくても快適に」暮らせる家は十分可能です。「無駄を省いたスマートな家づくり」が広がっている印象です。
ただし、家のサイズは小さくなっているのに、価格は上がっている。つまり「坪単価が上がっている」ことも事実です。
これは大手ハウスメーカー中心に建物価格が高すぎるという側面もあります。もちろん、資材価格の上昇や人件費の高騰が背景にあるので、会社が存続するためにも値上げは仕方ないかもしれませんが、それにしても「価格を上げすぎ」という現状が浮き彫りになっていると言えますね。
だからこそ、「予算配分の優先順位」と「ムダを省いた設計」によるスマートな家づくりが重要です。
■世帯年収
738万円(令和2)→907万円(令和6)/+22.9%
家を建てている方がどれくらいの世帯年収かという平均値です。「家を建てた世帯」の平均年収であり、「年収900万円ないと家を建てられない」という意味ではありません。
1番のボリュームゾーンは「600万円以上800万円以下」が全体の20.7%、次いで「400万円以上600万円以下」が20.0%になります。また、過去の推移を見ると「800万円以上の世帯年収の方」の割合も、過去5年間で最高水準になっています。
ただ、収土地・建築費の高騰が年収の伸び以上のペースで進んでいるため、「家が買いやすくなった」とは言いにくい状況です。年収の増加はローン上限を広げる助けにはなりますが、安心材料には直結しないと考えるのが現実的ですね。

■金利タイプの選び方
変動金利を選んだ人:69.6%(令和2)→73.1%(令和6)
∟全国:57.0%(令和2年)→84.5%(令和6年)
∟大都市圏:73.1%(令和2年)→96.5%(令和6年)
変動金利の選択割合は上昇傾向で、直近調査でも全国・三大都市圏ともに高水準でした。超低金利が続いているため、依然として変動派が主流。しかも全国都市部ともに変動金利を選んだ割合が過去最高です。
これは固定金利が上がってきているので変動金利に流れているのが要因かもしれません。
【変動金利で住宅ローンを組む方必見!】2025年1月24日の日銀発表の利上げで負担はどう変わる?https://www.taiyo-co.com/column/64708
以前の家づくりコラム内でも言及しておりますが、日本銀行は金利を上げていく政策を進めています。変動金利を組んでいる方は分かると思いますが、0.25%、0.5%と徐々に上がっていますね。10年前に変動金利で住宅ローンを組まれた方であれば0.6%が1.0%くらいになっているのではないでしょうか。また、変動金利は今後も上がっていくという見通しになっているので、変動金利か固定金利の選択は本当に難しいです。
この話をすると長くなってしまうので、最近のトレンドを少しお伝えします。
7月の参院選では与党が議席を減らし、「消費減税や給付の拡充」を公約に掲げた政党が躍進しました。長期金利や固定金利の見通しは、こうした政策期待や市場の需給動向にも影響を受けます。
影響を受けることで何が起こるかというと、政策によって「国債価値が落ちる」可能性が考えられます。実際に近年、国債の価格が下落する局面が続いたこともあります。そうなった場合、国債の金利を上げないと買い手がつかないため金利を上げていきます。
国債の長期金利が上がっていくと固定金利が上がっていきます。固定金利の代表格が「フラット35」です。今後は上昇していく見通しになっています。
固定金利と変動金利の差が1%~1.5%くらいです。どちらを選んだほうが良いかは未来で答え合わせするしかありませんので全く分かりません。
変動金利を選択する方が増えたのは、金利が低い間に繰り上げ返済の原資を貯めて住宅ローン控除の恩恵をしっかり受けた後に返済するという賢い人が増えたのではないかと思います。
いずれにしても変動金利は、支払いを抑えやすいメリットは大きいですが、将来の金利上昇リスクも忘れてはいけません。「月々の支払いを抑えつつ、繰上返済できる余力を残す」ことが安心のポイント。変動金利を選ぶなら、家計に余白を作ることが絶対条件だと思います。

■設備のトレンド
・宅配ボックス
設置率:全国38.1%/三大都市圏41.9%
まだ普及率は4割程度と意外と多くないですが、共働き世帯を中心に導入が進んでいます。再配達削減にもつながる便利さが評価され、これからの標準装備になりそうです。
これから宅配費用も上がっていくと思われますので、設置したほうが良いと思います。
・太陽光発電
設置率:全国57.3%/三大都市圏59.9%
(令和2年度の44.7%から大幅増加)
いまや半数以上の注文住宅で導入済み。太陽光発電は必須ではありませんが、今後も電気代の値上がりが見込まれる中で、電気の消費量も上がっていくと思いますので、設置したほうが良いかと思います。
蓄電池やHEMSと組み合わせれば、災害時の安心にもつながります。
住宅に関する調査資料を載せておきますので、皆さんも興味があれば見てくださいね。
「令和6年度住宅場動向調査報告書」
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001900667.pdf
データを見ると「家づくりは高くなった」と感じがちですが、太陽ハウジングのように堅実で適正な価格で建てられる選択肢もあります。数字に振り回されず、ご家族のライフスタイルに合った“ちょうどいい家づくり”を考えていくことが大切だと思います。
全国平均と比べても、太陽ハウジングの家づくりは 「適正価格 × 安心品質」 を実現しています。
「実際に私たちの予算でどんな家が建てられるの?」と気になった方は、ぜひ一度ご相談ください。きっと数字以上の安心を感じていただけるはずです。
今回のように、データで「土地相場」「総コスト」「世帯年収」「延べ床面積の傾向」などを知ることで、家づくりのリアルな感覚が見えてきます。
もし「自分たちの場合はいくらくらい?」「希望の広さで無理なく建てられる?」と気になったら、ぜひ家づくり相談会やモデルハウスへお越しください。
太陽ハウジングでは、あなたの予算・土地・ライフスタイルをもとに、現実的で無理のないプランをご提案します。
▼希望に合う土地が見つからない方へ
「気になる土地が見つからない…」「ネットで探してもピンとくる情報がない…」
そんなときは、太陽ハウジングの『非公開土地情報』をご活用ください。
太陽ハウジングでは無料の会員登録をしていただいた方限定で公開しています。