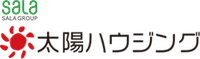太陽ハウジングの家づくりコラム
太陽ハウジングの家づくりコラム

- TOP>
- 家づくりコラム
2023.01.26
快適な住まいに欠かせない断熱の種類とは?【壁編】
こんにちは。太陽ハウジングです。
少し間が空いてしまいましたが、住宅の断熱の話の続きです。今回は壁の断熱についてご紹介します。
壁の断熱方法については「充填断熱(内断熱)」「外張り断熱(外断熱)」「付加断熱」の3種類があります。まずはそれぞれの特徴について見ていきましょう。

●充填断熱(内断熱)の特徴とメリット・デメリット
柱の間に断熱材を入れ込んでいく工法となります。柱の間に断熱材を施工するので、余分なスペースが不要であることと、コストが低いことがメリットです。一方で、柱部分には断熱材がないため、そこだけ熱が伝わりやすいことと(寒冷地以外は関係ないかもしれませんが)、配線や配管がある部分は複雑な施工を必要とするため気密断熱に影響が出やすいというのがデメリットとなります。
●外張り断熱(外断熱)の特徴とメリット・デメリット
柱の外側を断熱材で巻き、建物全体を包み込む工法となります。断熱材を構造体の外側に貼り付けるため比較的施工しやすいということと、気密性が高いということがメリットです。一方で、断熱材の上に外壁材をとめるので断熱材を厚くできないこと、外的要因によって経年劣化の不安があること、先ほどご紹介した充填断熱(内断熱)よりコストが高くなることがデメリットとして挙げられます。
●付加断熱の特徴とメリット・デメリット
充填断熱(内断熱)と外張り断熱(外断熱)の両方を行う工法です。それぞれの良いところを取り入れることができます。断熱性能や気密性能が高い、温度ムラや断熱欠損、壁内結露が起こりにくいといったことがメリットです。一方で壁が厚くなることとコストが高いことがデメリットといえます。

●結局壁断熱はどの方法が一番いいの?
以上の特徴を踏まえると、充填断熱(内断熱)より外張り断熱(外断熱)、外張り断熱(外断熱)より付加断熱のほうが良さそうと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、実は「これが一番良い!」という正解はありません。というのも、断熱は工法の違いよりも、「どのような断熱材を使っているか?」「厚みが何ミリのもの使っているか?」といった違いで断熱性能の差が出るからです。
たとえば、先ほどもご説明したとおり、外張り断熱(外断熱)には「断熱材の上から外壁材をとめるため断熱材を厚くできない」というデメリットがあります。この工法を採用しているほとんどの住宅会社は厚さ30~40ミリの断熱材を使用しています。これは充填断熱(内断熱)の半分もしくは半分以下の厚みです。
確かに外張り断熱(外断熱)は気密性が高いのですが、実際には充填断熱(内断熱)で分厚い断熱材を入れたほうが高い断熱効果を得られることになります。わざわざ高い費用を払って外張り断熱(外断熱)を選択するよりも、充填断熱(内断熱)のほうが、コスパがいいケースも多いのです。
ただ、鉄骨造の場合は柱が熱を通しやすい鉄でできているので、構造体を覆う外張り断熱(外断熱)のほうに軍配が上がります。お金がかかってでも温度ムラをなくして快適な住環境を作りたいというのであれば、付加断熱が一番です。
人それぞれ家づくりの予算には違いがあり、地域や構造によっても最適な選択肢は変わってきます。充填断熱(内断熱)じゃないといけない!外張り断熱(外断熱)じゃないといけない!付加断熱じゃないといけない!ということはありません。

●まとめ
それぞれの工法の特徴を把握し、施工する住宅会社がデメリットをどのように補っているかを知っておくことで、快適な空間づくりと無駄な出費を抑えることにつながります。