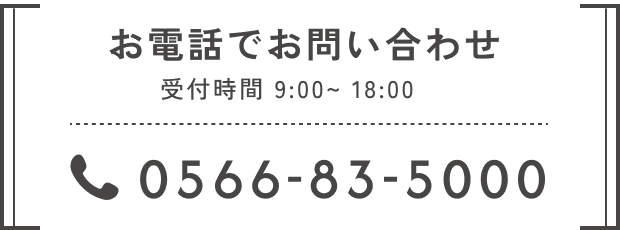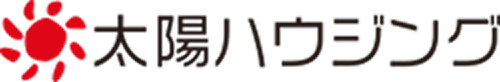COLUMN
家づくりコラム
地震保険だけで大丈夫?「上乗せ特約」の補償額・保険料・必要な家庭とは?
こんにちは、太陽ハウジングです。
地震大国・日本に暮らす以上、南海トラフ巨大地震や首都直下地震のリスクは避けて通れません。
もし、明日突然の地震で自宅が住めなくなったら…。
住宅ローンはそのまま残り、仮住まいの家賃も必要になります。地震保険は生活再建の“最低限の資金”を支える制度ですが、実際の再建費用をすべてカバーできるわけではありません。
特に住宅ローンや子育て世帯にとっては、万一の際に必要な資金が大幅に不足する可能性もあります。そこで注目されるのが「地震保険の上乗せ特約」です。
今回のコラムでは、本当に必要なのか、どんな家庭に向いているのか。今回は補償内容から保険料水準、加入を検討すべき人まで、具体例を交えて整理して、わかりやすく解説します。

■地震保険だけでは足りない現実
地震保険は、公的色の強い官民共同制度で「生活再建の最低限の資金」を目的としています。地震保険は火災保険金額の30%~50%の範囲でしか契約できず、上限も建物5,000万円・家財1,000万円に制限されています。
たとえば火災保険3,000万円なら、地震保険はその半分の 1,500万円が上限。つまり、全壊しても再建費用をすべてカバーできるわけではありません。
損害認定も「全損・大半損・小半損・一部損」の区分で行われ、主要構造部に至らない損傷は支払対象にならないケースもあります。
■再建費用と不足額
木造住宅を建て直すには2,500万~3,500万円程度かかるのが一般的です。
仮に 再建費用3,000万円・ローン残高2,000万円 のケースでは、地震保険だけでは不足が明らかです。
・地震保険(50%契約):1,500万円
・再建費用:3,000万円
・自己負担:1,500万円+ローン返済の継続
ここに生活費や仮住まいの家賃も加わるため、地震保険単体では心もとないのが現実です。
■「上乗せ特約」の基本的な仕組みとメリット
こうした不足を補うために損保会社が販売しているのが「地震上乗せ特約」です。
仕組みはシンプルで、地震保険で支払われる金額と同額を上乗せで受け取れるというもの。たとえば地震保険1,500万円なら、全損認定時にはさらに1,500万円が上乗せされ、合計3,000万円を受け取れる可能性があります。
ローン残高や生活費の確保を考えれば、大きな安心材料になりますね。
■「上乗せ特約」でどこまで補えるか
火災保険3,000万円・地震保険1,500万円に「上乗せ特約(同額1,500万円)」を付けたケース。
全損時
地震保険 1,500万円 + 上乗せ 1,500万円 = 3,000万円
⇒ 再建費用をほぼカバー可能
半損時(損害割合50%超70%以下)
地震保険 750万円 + 上乗せ 750万円 = 1,500万円
⇒ 再建費用の不足分は数百万円~1,000万円以上
一部損時(損害割合3%以上20%未満)
地震保険 75万円のみ、上乗せ対象外
⇒ 実際の修繕費(例:200万円)との差額は自己負担

■「上乗せ特約」の仕組み
火災保険に任意で付けられるオプションで、大きく2タイプあります。
・地震危険等上乗せ特約
地震保険が支払われた場合に同額を上乗せし、合計で火災保険金額(最大100%)まで補償可能。ただし対象が「全損・半損のみ」といった制約があり、小半損や一部損は対象外のことがあります。
・地震火災費用保険金の拡張特約
地震が原因の火災について、本来は火災保険金額の5%(上限300万円)しか出ませんが、これを30%や50%に拡大するもの。ただし「火災」限定であり、地震そのものによる損壊・流失は対象外です。
■保険料の水準と注意点
上乗せ特約は、契約期間が1年のみで長期契約による割引が使えません。そのため毎年更新が必要で、保険料も上がる可能性もあります。
今回の試算条件(火災保険3,000万円、地震保険1,500万円、耐震等級3、愛知県知立市、T構造)では、以下の結果となりました。
・地震危険等上乗せ特約
年額 39,110円
・地震火災費用保険金の拡張特約(地震火災30プラン)
年額 31,370円(地震家財含む)
・地震火災費用保険金の拡張特約(地震火災50プラン)
年額 56,280円(地震家財含む)
いずれも地震保険料に上乗せして追加で必要になる金額です。
重要な注意点
さらに注意すべきなのは、この試算結果は「T構造かつ耐震等級3」という最も有利な条件でのものだという点です。
もし建物が 木造(H構造・M構造)や耐震等級を取得していない場合、損害リスクが高いと判断され、保険料は大幅に上がります。
実際に、地震保険料に加えて年7〜12万円ほど増えるケースも少なくありません。特に耐震性が低い建物では、保険料負担が跳ね上がるため「毎年支払えるのか」を冷静に検討する必要があります。
また、地震保険そのものは国が関与する非営利制度の商品ですが、この「地震危険等上乗せ特約」や「地震火災費用保険金の拡張特約」は損保会社が独自に販売する営利商品です。そのため、保険料が高めに設定されるのは避けられないという点も理解しておくことが大切です。

■税制面のメリット
地震保険料には「地震保険料控除」があり、特約部分も多くの場合この控除対象に含まれます。年末調整や確定申告で数千円から1万円程度の節税できる税制上のメリットもありますが、年間のコスト増と比べれば限定的なメリットといえるでしょう。
■加入を検討すべき人は?
地震保険はあくまで「最低限の生活再建資金」を補う制度であり、上乗せ特約を付けることで火災保険金額相当まで補償を引き上げることが可能になります。再建にかかる費用やローン返済の負担を考えれば、大きな安心につながるでしょう。
ただし、実際に支払いの中心となるのは「全損・半損」といった大規模な被害時であり、「一部損」では補償が受けられない場合があること、そして年間7〜12万円前後という高額な保険料を毎年負担し続ける必要があることは大きな制約です。
したがって、上乗せ特約が効果を発揮するのは以下のようなご家庭です。
・住宅ローンがまだ多く残っている家庭
・子どもが小さく、生活再建にまとまった資金が必要な家庭
・住宅ローンに加え、仮住まい家賃など二重負担のリスクがある家庭
一方で、老後資金が十分にあり再建の必要が小さい世帯にとっては、必ずしも必要な商品ではありません。
結局のところ、家族構成やローン残高、将来の生活設計によって必要性が大きく変わるため、「いざという時の安心」と「毎年の負担」のバランスを見極め、自分の家計と照らし合わせて検討することが不可欠です。

地震保険の上乗せ特約は、すべての家庭に必要な万能の備えではありません。
しかし、住宅ローンが多く残っている方や子育て世帯、二重ローンリスクを抱えるご家庭にとっては、万一の生活再建を支える大きな安心材料になります。
一方で、老後資金が十分にあり再建の必要が小さい世帯にとっては、必ずしも加入すべき商品ではありません。
重要なのは、「いざという時の安心」と「毎年の負担」のバランスを冷静に見極めること。まずはご自身の家計・ライフプランに合わせて試算を行い、わが家に本当に必要かを考えることから始めてみてください。
保険も構造も、住まいの安心を支える大切な要素です。
しかし、それぞれの条件や家族構成で必要な備えは異なります。「うちの場合はどうか?」
そんな疑問をお持ちの方は、どうぞお気軽に家づくり相談会やモデルハウスにお越しください。
太陽ハウジングは、構造や将来設計まで含め、「無理なく安心できる家づくり」をサポートいたします。
▼家づくり相談会・建物見学会はこちら
イベント情報を見る
▼モデルハウスはこちら
モデルハウスを見る