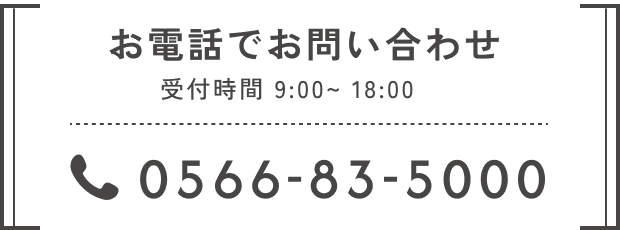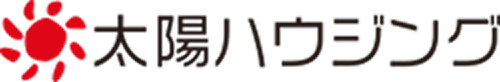COLUMN
家づくりコラム
家を守る保険シリーズ②【地震保険は本当に必要?】後悔しないための加入判断ポイントとは?
こんにちは、太陽ハウジングです。
前回の「家を守る保険シリーズ①【火災保険の選び方と注意点】」では、火災保険の基本補償から特約の取捨選択まで、住まいの立地やライフスタイルに合わせた選び方をお伝えしました。
※第1回をまだお読みでない方は、ぜひこちらもご覧ください。
今回の第2回では、火災保険とセットで検討されることが多い「地震保険」について詳しく解説します。
お客さまからよく聞かれる声があります。
「うちは耐震等級3のしっかりした家だから、地震保険は不要でしょ?」 「制震ダンパーも付けたし、もう十分安心」 「火災保険に入っているから、地震で火事になっても大丈夫よね?」
家づくりでしっかりと地震対策をされた方ほど、このようにお考えになるのは自然なことです。確かに、耐震等級3や制震装置は地震に対する非常に有効な備えです。
しかし、重要な事実があります。
2024年の能登半島地震や1995年の阪神・淡路大震災の被害状況を見ると、その判断だけで本当に十分なのでしょうか。地震による被害は建物の倒壊だけではありません。津波や火災、土砂崩れなど、耐震性能では防ぎきれない二次災害が暮らしを直撃することもあります。
例えば、能登半島地震では、築年数の浅い耐震等級3の住宅でも、液状化や地盤のずれによって傾きや基礎破損が発生し、修復に数百万円単位の費用が必要になった事例もあります。
大地震では揺れによる直接被害だけでなく、津波・火災・土砂崩れなどの二次災害が暮らしを直撃することもあります。しかも火災保険では、地震を原因とする損害は補償されません。つまり、地震が原因で発生した火災や倒壊は、地震保険に加入していなければ一切補償されないのです。
一方で、地震保険は補償額や支払基準に特徴があり、それを理解せず「とりあえず加入」すると「思ったほど保険金が出ない」という後悔にもつながります。
そこでこのコラムでは、地震保険の仕組みと特徴、メリットと限界、建物性能・立地条件・家計の3つの視点からの判断基準を整理して、加入判断の参考にしていただけるように解説します。

■地震保険の基礎知識
制度の歴史と特徴
地震保険は1966年に開始された、国と民間保険会社が共同で運営する特殊な制度です。関東大震災(1923年)の教訓を受け、巨大地震による甚大な被害にも対応できるよう、国が再保険を引き受ける仕組みになっています。
対象となる災害
地震保険が補償する災害は以下の3つです:
・地震による建物・家財の損壊
・津波による流失・損壊
・火山噴火による損害
火災保険との決定的な違い
重要なポイント:地震が原因で発生した損害は、火災であっても火災保険では一切補償されません。
例えば:
- 地震による電気配線の損傷で発生した火災
- 地震でガス管が破損し、引火した火災
- 地震で倒れた暖房器具から広がった火災
これらはすべて地震保険でしか補償されない被害です。
補償金の使い道
地震保険の保険金は使途が自由です。建物の修理に限らず、生活費、引っ越し費用、子どもの転校費用など、生活再建に必要な様々な用途に使用できます。
■地震保険の加入条件と仕組み
火災保険とセット加入が必須
地震保険は単独では加入できず、必ず火災保険とセットでの契約となります。ただし、火災保険契約後でも途中から地震保険を追加することは可能です。
補償額の上限と制限
地震保険は火災保険金額の30~50%の範囲内でしか契約できません。
例:火災保険金額が3,000万円の場合
・地震保険の契約可能額:900万円~1,500万円
・契約上限:建物5,000万円、家財1,000万円
つまり、もし全壊と認定されても受け取れるのは建物再建費用の半額程度。残りは自己負担となります。
阪神・淡路大震災では、全壊世帯の再建費用は平均2,500万~3,000万円とされており、地震保険だけでは不足する現実がわかります。
なぜこのような制限があるのか?
南海トラフ地震のような巨大地震では、同時に数十万件の被害が発生します。全額補償すると保険制度そのものが破綻してしまうため、地震保険は「完全復旧」ではなく「生活再建の足がかり」を目的としています。
■地震保険の損害認定の区分と支払額
地震保険では損害の程度によって支払額が変わりますが、「全壊」認定は意外に少ないのが実情です。
| 損害区分 | 損害割合 | 支払額(1,500万円契約) | 実例 |
| 一部損 | 20%未満 | 75万円 | 屋根瓦の崩落、外壁のひび割れ程度 |
| 小半損 | 20%以上40%未満 | 450万円 | 基礎や壁の一部損壊、室内の傾き |
| 大半損 | 40%以上70%未満 | 900万円 | 複数の壁や柱に構造的損傷 |
| 全壊 | 70%以上 | 1,500万円 | 建物の倒壊や大規模傾斜 |
重要なポイント:「全損」認定を受けるには損害割合が50%以上必要です。見た目に大きな被害を受けても、認定基準によっては「大半損」以下になることもあります。
実際、東日本大震災では「全壊」判定は全体の約4分の1にとどまり、多くは小半損や大半損に分類されました。全壊以外の場合は受け取れる金額も大きく減ります。
地震保険は、火災保険の保険金額の50%が上限です。
例えば、火災保険で3,000万円を設定していても、地震保険では最大1,500万円までしか補償されません。これは、仮に大規模地震で建物が全壊しても、保険金の満額が建築費全体をカバーできないことを意味します。
さらに注意すべきは、地震保険の損害認定の基準です。実際に全壊認定されるケースは多くなく、過去の震災でも全壊率は限られています。被害割合が20%未満の場合は「一部損」と判定され、保険金は契約金額の5%、つまり1,500万円契約なら75万円しか受け取れません。20〜40%の被害では「小半損」となり、支払額は契約金額の30%(同条件で450万円)にとどまります。
これらの支払い基準は、大規模地震後の生活再建に必要な費用感とは必ずしも一致しないため、実際にどの程度の保障が必要かを冷静に見極めることが重要です。
【事例Q&A】
Q.震度5強の揺れ。耐震等級3の家は倒れなかったが、外壁タイルが剥がれ落ちました。これも地震保険でカバーされる?
A.外壁タイルの剥落だけでは、地震保険の対象外となる可能性が高いです。
地震保険は「主要構造部(柱・梁・屋根・基礎・外壁そのものなど建物を支える部分)」に損害があった場合に適用されます。タイルはあくまで仕上げ材であり、構造体そのものではないため、タイルだけの損傷では対象外と判断されるケースが多いです。
ただし、タイルの剥落によって下地や外壁の構造体にまで損傷が及んでいれば、「一部損」と認定される場合があります。その場合に支払われるのは契約している地震保険金額の5%です。
例えば、火災保険3,000万円に加入の場合、地震保険金額は50%の1,500万円
一部損の支払額
1,500万円 × 5% = 75万円
修繕費が200万円だった場合、残りの125万円は自己負担となり、全額が補償されるわけではありません。
Q.ローンがまだ2,000万円残っているAさん。もし地震で住めなくなったら…?
A.家が全壊し住めなくなっても、住宅ローンの返済はなくなるわけではありません。
地震で自宅が倒壊しても、金融機関との契約は残るため、ローン返済は続きます。つまり「住めない家にお金を払い続ける」状況になり得ます。
例えば火災保険3,000万円に加入している場合、地震保険の上限はその半額の1,500万円。
全壊し「全損」と認定されても、受け取れるのは1,500万円までです。ローン残高2,000万円を抱えているとすると、500万円は借金として残る計算になります。
さらに実際の生活では、仮住まいの確保や引っ越し費用、新居の購入や家具・家電の買い直しなども必要になります。つまり地震保険は「ローンを消す保険」ではなく、生活再建のための最低限の資金と捉えるのが現実的です。

■加入が必要とされる背景
過去の地震での教訓
・阪神・淡路大震災(1995年)
全壊:約10万棟
火災による焼失:約7,000棟
地震保険加入率:わずか3.1%
当時は地震保険の認知度が低く、多くの被災者が自己負担で再建を余儀なくされました。
・能登半島地震(2024年)
全壊:約8,500棟(2024年10月時点)
地震保険支払い見込み額:約1,700億円
(出典:石川県災害対策本部、損害保険料率算出機構)
全壊と認定された世帯は一部に限られ、多くは「半壊」や「一部損」に分類。保険金が期待より少なく、再建資金が不足したという声が目立ちました。
・愛知県西三河エリアの地震リスク
南海トラフ地震の想定(愛知県の被害予測より)
・今後30年以内の発生確率:70~80%
・西三河エリアの予想震度:6弱~6強
・沿岸部の津波高:最大3~4m
内陸型地震のリスク
・猿投-高浜断層帯
・阿寺断層帯
(出典:愛知県東海地震・東南海地震等被害予測調査)
■火災保険ではカバーできない地震由来の損害
火災保険は、地震が原因で発生した火災・損壊・津波被害を補償しません。
例えば、地震で起きた通電火災(停電後の復旧時に発火する火事)や、地震による地割れでの倒壊は、火災保険だけでは一切補償が受けられません。
熊本地震では、直接的な倒壊ではなく「家具転倒による壁損傷」や「瓦の落下による雨漏り」なども発生し、こうした被害も火災保険ではカバーされないため、地震保険の存在が重要になります。
■耐震等級3でも「絶対安全」ではない理由
許容応力度計算による耐震等級3や、制震ダンパーなどの制震装置は、過去の地震でも効果があることが統計から分かっています。
ただし、耐震等級3はあくまで「新築時の性能評価」です。
一度の大きな地震で構造躯体には少なからずダメージが生じ、その状態で2回・3回と地震が繰り返されれば損傷は蓄積します。
さらに、建物の老朽化、施工不良、雨漏りや壁体内結露による木材の腐食などによっても、耐震性能は年々低下していく可能性があります。
このように、どれだけ高い耐震性能を備えていても、建物は時間の経過や環境の影響によって少しずつ性能が低下していきます。
耐震等級3や制震装置は確かに強い味方ですが、それだけで将来にわたって全てのリスクをなくすことはできません。
また、地震の被害は揺れによる構造破損だけに留まらず、二次災害は耐震性能では防げません。
・地震火災(隣家からの延焼を含む)
・津波による流失
・液状化による地盤沈下
・土砂崩れによる損壊
これらはいかに耐震性能の高い家でも防ぐことができません。

■判断基準:4つの視点から検討
1. 建物性能
建物の耐震性能は地震保険の必要性を判断する重要な要素ですが、耐震等級だけで判断するのは危険です。
耐震等級による基本判断
耐震等級1以下の建物では大地震時の倒壊リスクが高いため、地震保険への加入を強く推奨します。一方、耐震等級2~3の建物は確かに地震に強いですが、それでも地震保険が不要というわけではありません。
性能は時間とともに変化する
重要なのは、耐震等級は「新築時の性能評価」だということです。経年劣化、雨漏りによる構造材の腐朽、施工不良の顕在化などにより、性能は徐々に低下する可能性があります。また、一度大きな地震を経験すると、見た目には問題がなくても構造躯体に微細な損傷が生じ、次の地震で被害が拡大することもあります。
免震・制震装置の限界
免震装置や制震ダンパーは揺れを軽減する効果がありますが、想定を超える地震では効果が限定的で、津波や火災などの二次災害には無力です。
2. 立地リスク
住んでいる場所によって、地震による被害リスクは大きく異なります。建物がどれだけ強くても、立地条件によっては甚大な被害を受ける可能性があります。南海トラフ地震の被害想定では、西三河でも津波や長周期地震動の影響が見込まれる地域があります。
高リスク立地の特徴
沿岸部では津波による流失や浸水のリスクがあります。急傾斜地や崖地近くでは、地震による土砂崩れで建物が損壊する危険性があります。住宅密集地では、隣家の倒壊や火災の延焼により被害を受けるリスクが高まります。
見落としがちな液状化リスク
河川沿いや埋立地では、地震により地盤が液状化し、建物が沈下や傾斜する可能性があります。建物自体は無事でも、地盤沈下により住み続けることが困難になるケースもあります。西尾市や碧南市の一部地域では、液状化マップで高リスクとされ、地盤沈下が想定されています。
ハザードマップの活用
自治体が公開するハザードマップで、津波浸水想定区域、土砂災害警戒区域、液状化危険度などを必ず確認しましょう。複数のリスクが重複する地域では、特に注意が必要です。
3. 経済的耐性
地震保険の必要性は、家計の経済状況によって大きく変わります。被災後の生活再建に必要な資金を、どの程度準備できているかが判断のポイントです。
住宅ローンが多く残っている場合
住宅ローンの残債が多い状況で被災すると、壊れた家のローンを払いながら新しい住まいを確保する「二重負担」が発生する可能性があります。このような状況では、地震保険は生活再建の重要な支えとなります。
貯蓄の準備状況
地震保険は建物の完全復旧を目的とするものではありませんが、当面の生活費、仮住まい費用、引っ越し費用など、被災直後に必要となる数百万円規模の出費をカバーできます。これらの費用をすぐに貯蓄から捻出できない場合は、地震保険の価値が高まります。
災害時の資金調達の困難さ
十分な貯蓄があっても、災害時は銀行のATMが停止したり、口座が凍結されたりする可能性があります。地震保険の保険金は比較的迅速に支払われるため、現金がすぐに必要な災害時には重要な資金源となります。
4. 家族構成とライフステージ
家族の状況やライフステージによって、被災時の影響や再建の難易度は大きく変わります。
子育て世代の特殊事情
子育て中の家庭では、被災時に子どもの転校手続き、新しい学用品の購入、心のケアなど、大人だけでは発生しない様々な費用や手続きが必要になります。また、教育費の負担が大きい時期でもあり、災害による追加出費は家計に大きな打撃を与えます。
高齢者世帯の再建困難
高齢者の場合、体力的・経済的に住宅の再建が困難になりがちです。住宅ローンを新たに組むことも難しく、地震保険の保険金が生活維持の重要な資金源となる可能性が高いです。
若い世代の選択肢
比較的若い夫婦であれば、被災後に住宅ローンを組み直して再建することも現実的な選択肢です。ただし、それでも当面の生活費や仮住まい費用は必要であり、地震保険があることで選択肢が広がります。
共働き世帯の収入リスク
共働きで収入が安定している場合でも、災害により職場が被災したり、転職を余儀なくされたりするリスクがあります。一時的に収入が減少する可能性も考慮して判断することが大切です。
■加入すべきかどうか
愛知県西三河エリアでは「原則加入推奨」
当社では、以下の理由から地震保険への加入を推奨しています:
- 南海トラフ地震の高い発生確率
- 内陸型地震のリスク
- 住宅ローンを抱える子育て世代が多い
- 耐震等級3標準仕様による50%割引適用
保険料の負担を抑える加入方法
1,補償額を適切に設定
全額カバーを目指さず、生活再建の足がかりとなる金額(建物1,000万円、家財200万円程度)でも十分な効果があります。
2.耐震等級割引を活用
太陽ハウジングの住宅は標準で耐震等級3のため、50%割引が適用されます。
3.長期契約で保険料を抑制
最大5年契約により、年払いより約10%の節約が可能です。
「最低限の補償」でも生活再建の足がかりに
地震保険は完全復旧が目的ではありませんが、被災直後の混乱期に「まとまった現金」があることで、以下のような効果があります。
・仮住まいの確保
・当面の生活費
・子どもの転校手続き費用
・就職活動や事業再開資金
・精神的な安心感
■加入判断チェックリスト
以下の項目をチェックしてみてください。
□ 住宅ローンが1,000万円以上残っている
□ 貯蓄で500万円以上の再建費用をすぐ出せない
□ 自治体のハザードマップで自宅の立地が津波・液状化・土砂災害危険地域に該当する
□ 周囲が住宅密集地で火災延焼リスクが高い
□ 建物の築年数が20年以上経過している、または耐震等級が低い
□ 南海トラフ地震の影響が予想される地域に住んでいる
3つ以上当てはまる場合は、地震保険加入を前向きに検討する価値があります。

■まとめ
地震保険は「被害を完全に補うためのもの」ではなく、「生活を立て直すための土台資金」と考えることが重要です。
耐震等級3や制震装置は確かに強力な備えですが、それだけでは防げないリスクもあります。
特に愛知県西三河エリアは南海トラフ地震の想定震源域に近く、決して地震リスクが低い地域ではありません。
「地震が怖いから何となく加入する」のではなく、建物性能・立地条件・家計への影響を総合的に判断した上で検討することが大切です。
火災保険だけでは地震による被害は一切補償されません。家の性能を維持する日々のメンテナンスと合わせて、経済面からの備えも整えておくことで、将来の不安を大きく減らすことができます。
太陽ハウジングでは、地震保険についてのご相談も承っています。お客様の住宅性能、立地条件、家計状況を踏まえた最適な判断をサポートいたしますので、お気軽にお声かけください。