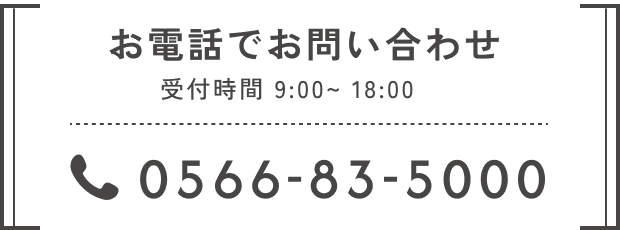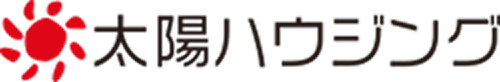COLUMN
家づくりコラム
地震だけじゃない!家づくりで考えるべき火災・台風・水害対策【第1回:火災対策】
こんにちは、太陽ハウジングです。
家づくりを始めると、多くの方がまず思い浮かべるのが「地震対策」ではないでしょうか。住宅会社の多くも、耐震性能や制震構造といった地震への備えを強くアピールしていると思います。
しかし、住宅を脅かす災害は地震だけではありません。
実際には、火災や台風、洪水といった被害も頻繁に発生しており、被害が大きくなるケースも少なくありません。
「テレビで見るような火災や水害、自分には関係ない」そう思っていませんか?
実際には、身近な地域でもこうした被害は起きており、決して他人事ではありません。
今回のコラムでは、住宅会社があまり教えてくれない「家づくりでできる火災・台風・洪水対策」を、3週に分けてお届けします。
初回のテーマは「火災対策」です。
新築時にしか取り入れにくい対策もありますので、これから家を建てようとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

■住宅火災は、身近なリスク
総務省消防庁のデータによると、全国では1日に平均100件前後の火災が発生しています。火災件数は年々減少傾向にありますが、それでも令和4年には建物火災だけで約1万件以上が報告されています。


出典:総務省消防庁_消防白書
オール電化住宅の増加や喫煙率の低下、住宅用火災警報器の普及などにより、火災件数は減ってきているものの、住宅火災による死者数は依然として高い水準にあります。
令和4年のデータでは、住宅火災による死者数は約1,000人。
自宅での火災は一瞬にして命を奪う危険性があるため、家づくりにおいて、しっかりと火災対策をしていく必要があることが分かりますね。
では、ここから火災に対する具体的な対策についてお伝えします。
火災対策は、大きく分けて 「家を建てる前にできる対策」と「住んだ後にできる対策」 の2つがあります。
【家を建てる前にできる対策】
■省令準耐火構造という選択
火災対策として、建築段階で取り入れられる最も効果的な方法のひとつが「省令準耐火構造」です。
省令準耐火構造とは、住宅ローン「フラット35」を取り扱う住宅金融支援機構が定める基準で、準耐火構造に準じた防火性能を持つ住宅構造のことを指します。
■「耐火構造」や「準耐火構造」との違い
省令準耐火構造と似た言葉に「耐火構造」や「準耐火構造」といったものがありますが、こちらは国土交通省が定める建築基準法上の区分で、防火地域・準防火地域で家を建てる際に必要とされる構造基準です。
一方で「省令準耐火構造」は、住宅ローンのフラット35を取り扱う住宅金融支援機構が定める基準です。
耐火構造・準耐火構造は法律で定められた基準のため、該当するエリアでは満たさなければ家を建てることができません。一方、省令準耐火構造は任意の仕様なので、建築そのものに制限はありません。
■省令準耐火構造の3つの特徴
省令準耐火構造は、主に以下の3つの特徴を持っています。
①近隣で火災が起きても延焼しにくい
屋根・外壁・軒裏など、隣家からの火の影響を受けやすい部分に不燃材料を使用することで、外部からの延焼リスクを低減します。
②室内で火災が発生しても外に燃え広がりにくい
火災は発生しても周囲に燃え移るものがなければ徐々に鎮火していきます。そのため、室内の壁や天井には石膏ボードなどの耐火性の高い建材を使用することで、万が一火災が起きても、火の広がりを抑えて他に燃え移るまでの時間を稼ぎ、避難・初期消火の時間を確保できます。
③火災が隣室に拡大しにくい
万が一部屋で火災が発生した際に、隣室へと燃え広がる速度を抑えられることです。
火は天井裏や壁内を通じて隣室へ広がりますが、省令準耐火構造では「ファイヤーストップ材(防火断熱材)」などを使用して、火の通り道を遮断し隣室へと燃え広がる速度を抑えられます。
■省令準耐火構造のメリット
・火災保険料の大幅割引
保険上、木造住宅は「H構造」と「T構造」に分類され、省令準耐火構造はT構造扱いとなり、鉄骨造と同等の低料率が適用されることから、火災保険料の大幅な割引を受けられるケースがあります。
具体的には、建物の火災保険金額3000万円の場合、現在の火災保険期間の最長年数5年間でH構造が約20万円、T構造は約11万円と約半額になります。
省令準耐火構造にすることは、コストアップになります。
会社によって違いますが、30坪の建物で約15〜25万円の追加費用が目安です。
しかし、火災保険料の差額で約15年で元が取れる計算となり、命を守りながら保険料も節約できる合理的な選択になりますので、住宅会社が省令準耐火構造の対応ができるということであれば、施工していただいたほうが良いと思います。

■太陽ハウジングは「標準で省令準耐火構造」
ちなみに、太陽ハウジングの建物は地震対策だけでなく火災対策にも配慮し、すべての建物で省令準耐火構造を標準採用しています。
追加費用なしで、安心・安全な住まいをご提供しています。
このように、省令準耐火構造は「火災に強い家づくり」の基本ともいえる存在です。
これから家を建てる方は、ぜひ防災の視点からも構造を見直してみてください。
■断熱材と火災リスクの意外な関係
家づくりで「断熱材」と聞くと、快適性や省エネ性能を重視する方が多いかもしれません。しかし、断熱材の選び方が火災時のリスクにも関わってくるということは、あまり知られていません。
断熱材にはさまざまな種類があり、それぞれに燃えにくさの度合いや火災時の挙動が異なります。
住宅でよく使われる断熱材には、以下のようなものがあります。
| 断熱材の種類 | 特徴 | 火災時のリスク |
| グラスウール | ガラス繊維でできた不燃材。広く普及。 | 不燃性で延焼リスクが低い。 |
| ロックウール | 鉱物を高温で溶かした不燃材。耐火性能が高い。 | 高温でも燃えにくく、有毒ガスも出にくい。 |
| 発泡ウレタン系 | 吹き付けタイプで気密性が高い。 | 可燃性あり。黒煙や有毒ガスを発生するリスクがある。 |
| ポリスチレンフォーム | 床下などに使われるボード型断熱材。 | 難燃処理されていても燃焼の可能性がある。 |
なかでも「発泡ウレタン系断熱材」は、断熱性能が高く施工しやすいことから人気ですが、万が一火災が発生した際には、発泡ウレタンは無色透明の有毒ガスを発生する可能性がある素材とされています。
火災は火そのものだけでなく「煙とガス」で命を奪うことが多いため、こうしたリスクも見逃せません。
■見えない部分こそ安心できる素材を
断熱材は建物の中でも「住んでから見えなくなる部分」です。だからこそ、素材選びは性能だけでなく、安全性や信頼性の視点でも選ぶ必要があります。
また、火災への備えは素材だけでなく、断熱材の施工方法や、防火区画の設計によっても左右されます。「きちんとした計画・監理のもとで施工されているか」も、安全性に大きな影響を与えるのです。
■太陽ハウジングの断熱材は「燃えにくさ」も標準仕様
太陽ハウジングでは、住まう方の命と資産を守るため、断熱材にも火災リスクへの配慮を標準としています。
・床には押出法ポリスチレンフォーム
断熱性と耐水性に優れたボード型断熱材。床下でも腐りにくく、適切な施工により火災時の延焼リスクを抑えられます。
・壁・天井裏にはロックウール
鉱物から作られた不燃性の断熱材で、非常に高い耐火性を持っています。高温でも燃えにくく、有毒ガスや黒煙の発生も少ないため、万が一の火災時でも避難時間の確保や初期消火の可能性を高めてくれる素材です。
家づくりでは、断熱性能や省エネ性能に目が行きがちですが、「燃えにくいかどうか」という視点も命を守る家づくりには欠かせません。快適さだけでなく、もしもの時に家族を守れる住まいをつくるために、こうした見えない部分にもこだわりを持っている住宅会社で建てていただきたいです。

【住んだ後にできる対策】
家を建てたあとも、日々の暮らしの中で火災のリスクを減らすことは十分に可能です。
まずは、住宅火災の原因を知るところから始めましょう。
意外に思われるかもしれませんが、住宅火災の原因で最も多いのは「コンロ(ガスコンロ)」です。
■第1位:ガスコンロ
▶ IHクッキングヒーターにすれば、火災リスクは大幅に低下します。
IHは直火を使わないため、布や紙などへの引火が起きにくく、火災リスクが非常に低いのが特徴で、小さなお子さまや高齢のご家族と暮らしているご家庭には特におすすめです。
鍋を振ったり自動調理機能を使いたいならガスコンロもありだと思いますが、使い方に注意し、周囲に燃えやすいものを置かないようにしてください。
調理中の「ちょっと目を離す」は、火災の大きな原因になるため、十分ご注意を。
■第2位:たばこ
▶ 寝たばこ・不適切な場所への放置が火災の引き金に。
喫煙が原因の火災は、死亡事故につながるケースが多いのも特徴です。
・灰皿を使わず、飲みかけの缶や空き瓶に吸い殻を入れる
・寝たばこをしてしまう
・ベランダや布団近くなど、燃えやすい場所での喫煙
これらは、いずれも非常に危険です。
お金もかかりますし、健康のためにも、火災予防のためにも、たばこは吸わないことをおすすめします。
■第3位:電気機器・配線まわり
▶ 見落としがちな「コンセント」や「家電の劣化」に注意。
火災原因として増えているのが、電気による火災。特に気をつけたいのは以下のようなポイントになります。
・トラッキング現象
コンセントの差し込み口にホコリがたまり、湿気で発火する現象です。差し込み口が中途半端に刺さっていると埃も溜まりやすくなります。定期的な掃除と、しっかり差し込むことが大切ですね。
・たこ足配線・許容電力オーバー
延長コードやタコ足配線を長期間使い続けると、発熱・発火のリスクが高まります。配線はなるべく分散させ、熱を持ちやすい家電は専用回路など単独で使うのが理想です。
・古い家電の使用
調理家電やヒーターなどは、経年劣化によりコードが傷んだり、内部で不具合が起こることがあります。長年使っていて「最近調子が悪いな、音がうるさくなってきた」と感じたら、耐用年数を確認して買い替えを検討しましょう。
■火災対策は「建てる前」も「建てた後」も大切
火災は、住宅災害の中でも最も身近で、そして一瞬で命や財産を奪ってしまう危険な災害です。「省令準耐火構造」や「燃えにくい断熱材」など、家を建てる段階での備えもあれば、日々の生活の中で意識しておきたい暮らし方の工夫もあります。
火災対策は建てる前も建てた後も、知っているかどうかで大きく変わります。
ご家族の安心と安全を守るために、「火災に強い家とは何か」を、ぜひ一度考えてみてください。

次回は「台風対策」をテーマにお届けします。
「地震だけじゃない!家づくりで考えるべき火災・台風・水害対策【第2回:台風対策】」
新築時に考えておきたい台風対策のポイントをわかりやすくご紹介します。
どうぞお楽しみに!