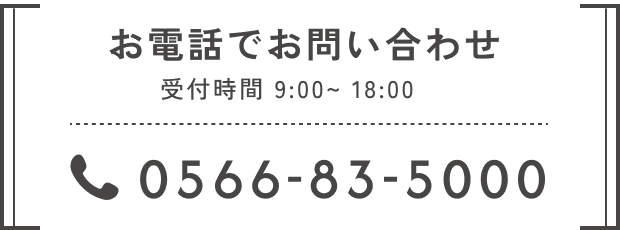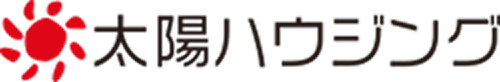COLUMN
家づくりコラム
地震だけじゃない!家づくりで考えるべき火災・台風・水害対策【第2回:台風対策】
こんにちは、太陽ハウジングです。
今回は、住宅会社があまり教えてくれない「家づくりでできる火災・台風・洪水対策」の「台風対策」についてお届けします。
前回は、「火災対策」についてお届けしました。コラムはこちら。
「地震だけじゃない!家づくりで考えるべき火災・台風・水害対策【第1回:火災対策】」
家づくりを考えるとき、災害対策の多くは「地震」に注目が集まりがちです。しかし、実際には毎年のように日本に接近・上陸する台風も、非常に大きな被害をもたらします。
台風は進路や勢力の予測が難しく、突然進路を変えたり、再上陸したりと「想定外」の被害が発生しやすい自然災害です。だからこそ、「自分の家は自分で守る」という意識が重要になります。
今回のコラムでは、家づくりの視点から考えるべき台風対策について、「家を建てる前」と「住んだ後」の2つに分けてお伝えします。
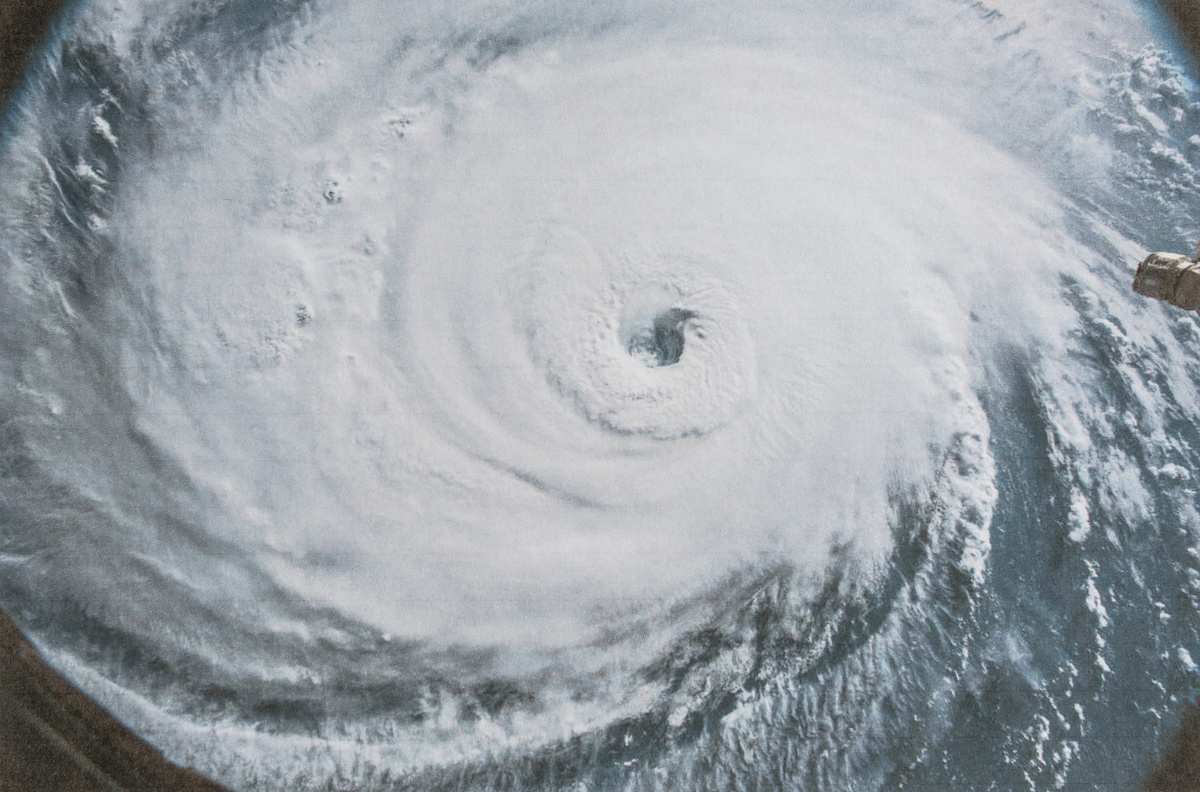
■そもそも台風とは?どのくらいの頻度で来るの?
台風は、熱帯の海上で発生する低気圧が発達し、強い風と大雨を伴って移動する現象です。気象庁によると、毎年平均20個前後の台風が発生し、そのうち日本に接近するのは約11個、上陸するのは約3個程度とされています。
また、台風のニュースでよく見る「中心気圧(ヘクトパスカル)」は、台風の勢力を示す指標のひとつで、数値が低いほど強い台風になり、風速も雨量も大きくなる傾向があります。また、進路の「右側(東側)」は、風が強く吹き込むため、左側(西側)よりも被害が大きくなりやすいと言われています。
近年では、沖縄から九州を通過する従来の進路だけでなく、太平洋側からダイレクトに上陸するケースや、一度通過した台風がUターンして再上陸するなど、予測しづらい動きも増えています。気象庁や民間の天気予報会社によっても進路予測に違いがあるほどで、「予測困難な災害」として年々注目が高まっています。
【家を建てる前にできる台風対策】
■大きな窓にはシャッター雨戸や防災ガラスを
まずは、最低限「安心できる居場所」を確保する 台風時には家族が自宅に留まることが基本です。だからこそ、少なくともリビングやダイニングといった家族が集まる空間には、「シャッター雨戸」や「防災ガラス」など、飛来物から守る対策を優先しましょう。
全窓に設置するのは現実的でない場合もありますが、「家族の命を守る空間」には最低限設けておいてください。
■軒の出・屋根形状・雨樋にも注意が必要
▶台風対策は窓だけではありません。屋根の形や軒の出、雨樋も実は風に対する影響が大きい箇所です。
・軒の出が長すぎると危険?
軒の出が長いデザインは日射遮蔽には有効ですが、台風のような強風時には風を受けやすくなり、屋根材が煽られたり、破損の原因となる場合もあります。地域の風向きや強さを考慮して、軒の出の長さは適切に設計しましょう。
・屋根形状は風の流れを意識したデザインを
「片流れ屋根」は見た目のスタイリッシュさと雨水処理のしやすさが魅力ですが、風を一方向に受け続ける構造になりやすく、強風時には浮き上がりやすいという欠点も。
風の流れをうまく受け流す「切妻屋根」や「寄棟屋根」など、風の通り道を考慮した形状の方がより安全性は高くなります。
ただし、デザインや敷地条件との兼ね合いもあるため、住宅会社と相談しながら「台風が多い地域ならではの屋根選び」を検討するとよいでしょう。
・雨樋は外れやすい要注意パーツ
雨樋は風雨にさらされる場所にあるため、台風時に最も破損しやすい部材のひとつです。
飛来物が当たったり、強風によって固定金具が外れたりすることで、雨樋が落下したり、変形するケースもあります。対策としては、以下のポイントが有効です。
・耐風試験済みの強化型雨樋を採用する
・金具のピッチ(間隔)を狭めて取り付ける
・軒樋(水平部分)だけでなく、縦樋(縦の排水管)も固定をしっかりと
・雨樋周辺の落ち葉やゴミを日頃から掃除して、風の抵抗を減らす
これらの工夫により、台風時の被害を大きく減らすことができます。

■台風対策のQ&A
Q. 隣の家の物が飛んできてガラスが割れたから、相手に請求できる?
A. 原則、請求できません。災害は「不可抗力」。自分の火災保険での対応となります。
災害による被害は、法律上「誰かに責任を問うことが難しい」とされています。たとえば、隣家の植木鉢や物干し竿が飛来してガラスが割れたとしても、それが台風などの自然災害によるものであれば、「加害者がいない=自分の火災保険で対応する」ことになります。
つまり、「災害リスクは自分で備える」というのが基本スタンス。保険も含めて自衛策を講じておくことが、安心して暮らすための重要なポイントです。
【住んだ後にできる対策】
台風がもたらす被害の中でも特に多いのが「停電」です。
最近は送電網の復旧も早くなってきていますが、長時間の停電に備えて日頃から準備しておくことが、安心して暮らすためのポイントになります。
以下の対策をぜひ参考にしてください。
■災害用非常バッグの中身を定期点検
非常用バッグの中に入れてある食品や飲料水の賞味期限、乾電池の使用期限は定期的に確認・入れ替えを。「いざというときに全部ダメになっていた」ということがないように、半年~1年に一度は中身を見直しましょう。
■車のガソリンは常に半分以上をキープ
停電時、車は移動できる「動く避難所」として活用できます。
エンジンをかければエアコンが使えますし、スマホの充電やラジオの視聴も可能。台風シーズンには特に、ガソリンを空っぽ近くまで減らさないよう意識するだけでも安心感が変わります。
■ポータブル電源を用意しておく
蓄電池ほど大掛かりな設備がなくても、小型のポータブル電源が1台あると非常に便利です。スマホやタブレットの充電、小型家電の使用、LEDライトの点灯、ラジオの活用などに役立ちます。
太陽光発電を搭載している場合は、日中に発電した電気で充電することも可能です。大容量でなくても構いません。「最低限の生活を維持する電力」を確保できるポータブル電源の配置をおすすめします。
■風で飛ばされやすい物は事前に片づける
台風被害が大きくなる原因のひとつが「飛来物」です。風によって物が飛ばされることで、二次被害が起こります。
以下のような物が加害の原因になりやすいので、注意が必要です。
・ベランダや庭にあるプランターや植木鉢
・物干し台、アウトドアチェア、折りたたみテーブル
・自転車、三輪車、子どもの遊具
・ゴミ箱や空の収納ボックス、園芸用品
・玄関付近にある傘、ダンボール
「自宅だけでなく、周囲の家に被害を与える可能性がある」という点です。
たとえば、飛ばされた物で隣家の窓が割れたり、車に傷がついたりしても、台風などの災害時は不可抗力とみなされ、加害者に責任が問われないのが一般的です。
とはいえ、「自分のせいじゃないからいいや」では済みません。ご近所との信頼関係にヒビが入ることもあります。今後も続くお付き合いを考えると、「飛ばさない工夫」こそが大切な配慮です。

■飛散を防ぐための3つの基本対策
・風が強くなる前に屋内に取り込む
・屋外に置く場合は、ロープなどでしっかり固定
・風に飛ばされやすい物はなるべく屋外に出さない
隣家やご近所への被害は、たとえ不可抗力でも信頼関係に影響します。
ちょっとした油断が、思わぬご近所トラブルにつながる恐れもあります。家の外周を一周見て、「これ、飛ぶかも?」という視点でチェックすることを日頃から持っておくと安心です。
■台風のときは外に出ない
「川の様子を見に行ったら流されてしまった」
「倒れた木を確認しに行って被害に遭った」
こうした事故はニュースで繰り返し報道されますが、実際に多くの方が命を落としている現実でもあります。
台風が接近しているときは、外の様子が気になっても出歩かないことが最大の防災。「自分の命を守るために家から出ない」という意識を、家族みんなで共有しておきましょう。

■台風対策は家づくりと日常の両面で考える
台風は進路や勢力の予測が難しく、直前になって急に被害リスクが高まることもあります。住宅の計画段階でできる対策、そして住んだ後に備えておくべき対策をあらかじめ考えておくことで、家族の命と暮らしを守ることにつながります。
特に近年は、台風の進路や勢力が従来の常識では予測しにくいケースが増えてきました。
「自分の家は大丈夫」と思わず、「もしも」を想定して備える姿勢が、結果的に被害を最小限に抑えます。
今回のコラムを参考にしていただき、ぜひご家庭でも台風への備えを見直してみてください。
【次回予告】
次回は、地震だけじゃない!家づくりで考えるべき火災・台風・水害対策【第3回:洪水・水害対策】をお届けします。
土地選びや間取り、設備の工夫など、住宅会社があまり教えてくれない水害対策を、家づくりの視点からわかりやすく解説します。
「うちは内陸だから大丈夫」と思っている方も、意外な落とし穴があるかもしれません。
地震・火災・台風と並んで、「水害」も見逃せないリスクです。ぜひ次回もご覧ください!