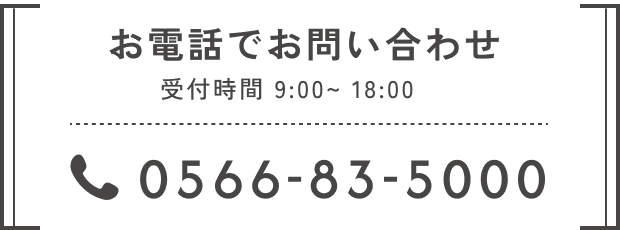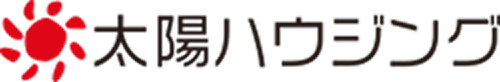COLUMN
家づくりコラム
家を守る保険シリーズ①【火災保険の選び方と注意点】とは?
こんにちは、太陽ハウジングです。
マイホームの完成が近づくと、多くの方が悩むのが火災保険の選び方です。
「火事のときにだけ使う保険」と思われがちですが、実は台風や豪雨による浸水、雹(ひょう)による窓や屋根の損傷、さらには漏水や盗難など、住まいを守る幅広い補償が用意されています。
しかし、近年は自然災害の増加を背景に保険料が上昇しており、2024年10月には過去最大の約13%値上げがありました。2025年9月と10月も数%程度の値上げや補償内容の見直しが予想され、加入のタイミングや内容の取捨選択がますます重要になっています。
とはいえ、補償を全部入りにすれば安心…というわけではありません。必要以上の補償は家計を圧迫し、逆に本当に必要な補償が不足していると、いざという時に大きな自己負担が発生してしまいます。
そこで今回のコラムでは、住まいの立地やライフスタイルに合わせて「本当に必要な補償」を見極めるためのポイントを、住宅と保険の両面から分かりやすく説明します。

■補償の「要・不要」を見極める基準
たとえば、火災保険の基本となる「火災」や「風災・水災」の補償はほぼ必須ですが、「漏水」や「外部からの物体衝突」などは家の間取りや立地によって必要度が変わります。
さらに、個人賠償責任保険や類焼損害特約などの特約は、ライフスタイルや近隣との関係性に応じて取捨選択が可能です。
大切なのは、「自分の家にとって本当に必要な補償」を見極めること。
地形や周辺環境、家族構成、普段の生活スタイルを踏まえて選べば、ムダな保険料を抑えながらも、災害や事故のときにしっかり備えられます。
このコラムでは、加入すべき基本補償、条件によって検討すべき補償、特約の取捨選択の考え方を具体的な事例や注意点とあわせて説明します。
火災保険を「とりあえず全部入る」から「納得して選ぶ」へ。
これから保険を検討する方も、更新を控えている方も、ぜひ参考にしてください。

■加入すべき基本補償
火災保険の補償内容の中にはさまざまな種類があります。特に、発生リスクや被害額が大きく、どの地域・住まいでも備えておくべき補償があるため必ず確認しましょう。
ここでは、災害や事故の際に生活再建の要となる“外せない基本”を説明します。
・火災(隣家のもらい火も補償)
火災保険の土台となる補償です。火事による建物や家財の損害はもちろん、隣家の火事による「もらい火」も対象になります。
日本の法律(失火責任法)では、隣家の火事が故意や重大な過失でない限り、火元からの賠償は受けられません。つまり、隣家の“うっかり火災”で自宅が被害を受けても、修繕費は自分持ちになります。
⇒ 全員必須加入。加入しないと火災保険の意味がありません。
・落雷(家電や屋根の損傷)
雷は屋根やアンテナに直撃するだけでなく、近くに落ちた雷(誘導雷)でも電化製品が故障することがあります。
例:パソコン、テレビ、給湯器、エアコンなどの修理・買い替え費用
特に最近はゲリラ豪雨とセットで発生する雷が増え、被害件数も増加傾向です。
⇒ 必須加入(多くの場合は火災保険に自動付帯)
・破裂・爆発(ガス漏れ事故など)
ガス漏れや可燃物の爆発による損害を補償します。都市ガス・プロパンガスどちらでも起こり得る事故で、爆発の衝撃で家全体が損傷するケースもあります。
⇒ 必須加入(基本補償に含まれることが多い)
・風災・雹災・雪災
台風による屋根の飛散、外壁や窓ガラスの破損、雹(ひょう)によるソーラーパネルの割れ、大雪によるカーポート倒壊などを補償します。
近年は雹の被害が全国的に増えており、被害額が高額になりやすい補償のひとつです。
⇒ 必須加入。発生頻度が高く、修理費用も高額になりやすい傾向があります。
・水災(洪水・土砂崩れ)
洪水・高潮・土砂崩れなどの被害を補償します。支払い条件は以下のいずれかです。
・損害が再調達価額の30%以上
・床上浸水
・地盤面より45cm超の浸水
ただし、水災補償は保険料が高めです。
ハザードマップで洪水・土砂災害リスクがある地域は必須ですが、全く該当しないエリアであれば加入を見送る選択肢もあります。
⇒ 高リスクはもちろん、ハザードエリア50センチ未満の低リスク地域でも必須加入。
■条件次第で検討すべき補償
すべてのご家庭に必要とは限らないものの、家の立地や間取り、生活環境によっては備えておくと安心な補償があります。自分の住まいの条件と照らし合わせながら検討しましょう。
・漏水(給排水設備の事故)
給排水管や設備の事故で室内が水浸しになった場合の補償です。
例:2階の洗面台の配管破損 → 1階天井や床が水濡れ被害
特に2階に水まわりがある家や築年数が経過した家はリスクが高くなります。
⇒ 保険料は年数千円程度。該当する間取りなら加入推奨。
・外部からの物体衝突
車の突入、飛来物、落下物による損害を補償します。
例:車庫入れ中に自宅の壁を破損、暴風で看板が飛来して窓ガラスが割れる
車両保険では建物修理は対象外のため、自己負担になるケースが多いです。
⇒ 車の運転に不安がある方や交通量の多い立地なら加入推奨。
・盗難
空き巣や強盗による損害を補償します。建物損害(窓・鍵の破損)や家財損害(現金・貴金属・家電など)も対象です。
共働き世帯や長期不在が多い家庭に向いています。
⇒ 保険料は安価。治安やライフスタイルに応じて加入。
・不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)
テレビの画面を割ってしまった、家具をぶつけて壁に穴をあけてしまったなど、思いがけない事故による家財や建物の損害を補償します。小さなお子さまやペットのいるご家庭では、加入しておくと安心です。
わが家でも、下の子が小さいときに物を投げて窓ガラスや液晶テレビにヒビを入れてしまったことがあり、この補償があって本当に助けられました。
⇒ 保険料は安くありませんが、家族構成や生活スタイルによっては検討の価値があります。免責金額を設定することで、保険料を抑えることも可能です。

■特約は取捨選択がカギ
火災保険には多くの特約がありますが、すべて付けると保険料が大きく膨らみます。生活スタイルや既存の保険とのバランスを踏まえ、必要な特約だけを選ぶことが家計と安心を両立するコツです。
・個人賠償責任保険(加入推奨)
日常生活で他人に損害を与えた際の賠償責任を補償します。
例:自転車で歩行者に衝突、子どもが他人の物を壊す、店舗の商品を破損
既に自動車保険や傷害保険で付帯していれば不要ですが、未加入なら火災保険とセットにするのがおすすめです。家族全員対象・国内外OK・保険料も安価でコスパ抜群。
・類焼損害特約/失火見舞費用特約(状況次第)
自宅からの火災で近隣に被害を与えた場合、法律上の賠償義務がなくても見舞金や補修費を補償します。
例:隣家の外壁がすす汚れ、ベランダの洗濯物が焼けた
地域での人間関係を大切にしたい方には有効ですが、必須ではありません。
・臨時費用特約(不要)
災害後の臨時費用(例:仮住まい費用)を補償しますが、限度額が低く、貯蓄で賄える範囲のことが多いです。保険料の割にメリットが小さいため優先度は低め。
・弁護士費用特約(不要)
事故相手に損害賠償請求する際の弁護士費用を補償します。ただし、個人賠償責任保険に示談交渉サービスが付いていれば十分対応可能です。過剰なリスクヘッジで保険料が高騰するのは避けましょう。
■家財保険はどこまで入ればいい?
火災保険は建物だけでなく、家の中にある家財にも補償を付けられます。家具や家電、衣類、食器、カーテンなど、引っ越しのときに持ち運べるものはすべて家財に含まれます。
家財保険の補償額は、世帯主の年齢や家族構成によって変わります。
下記は損害保険会社が用いる簡易評価表の一例です。
| 世帯主の年齢 | 独身世帯 | 夫婦のみ | 夫婦と子ども2人 | 夫婦と子ども3人 |
| 28~32歳 | 300万円 | 720万円 | 900万円 | 990万円 |
| 38~42歳 | 300万円 | 1,250万円 | 1,430万円 | 1,520万円 |
| 48歳以上 | 300万円 | 1,500万円 | 1,680万円 | 1,770万円 |
この表の通りに保険を掛けると、家財保険の金額はかなり高額になります。しかし、実際にはすべてを新しく買い替えるケースは少なく、必要以上に高い補償額に設定すると保険料が割高になります。
目安としては、独身や二人暮らしの場合は300万~500万円程度、家族世帯でも500万円程度までに抑えるのがおすすめです。
保険は全損の可能性が高いものに掛けるのが基本。家具や家電が全部同時に失われる確率は低いため、リスクと家計のバランスを考えて設定しましょう。

火災保険のよくある質問
Q.どこで火災保険に加入するのが良いですか?
A.価格重視ならネット保険、総合的な安心感なら住宅会社と提携している保険会社がおすすめです。
ネット保険は代理店を介さないため、保険料が圧倒的に安くなります。ただし、実際に事故や災害が起きたときのサポートは自分で保険会社とやり取りする必要があり、手間や時間がかかる場合があります。
一方、住宅会社と提携している保険の代理店であれば、保険料はネット保険より高くなりますが、次のようなメリットがあります。
1. 手続き・やり取りを代行してくれる
災害時、平日の日中に保険会社から連絡があっても、仕事や家事で対応できないことがあります。提携代理店なら、保険会社とのやり取りを住宅会社経由で代行してくれるため安心です。
2. 工事の手配が早い
提携代理店は住宅会社と連携しており、修理の見積もりや工事の手配もワンストップで対応できます。大きな台風の後、屋根がブルーシートのまま数日放置されるケースがありますが、これは業者の手配が追いついていないのが原因です。住宅会社経由なら、自社のお客さまを優先して屋根業者や工務店を確保してくれるため、復旧がスピーディーです。
・とにかく保険料を安くしたい → ネット保険
・いざというときの対応力や復旧スピードを重視 → 住宅会社提携の保険代理店
Q.支払い方法は「月払い」「年払い」「5年払い」のどれがおすすめ?
A.5年一括払いがおすすめです。
以前は10年や35年契約ができましたが、現在は最大5年まで。
保険料は毎年上昇傾向にあり、毎年更新するよりも5年分をまとめて支払うほうがトータルコストを抑えられます。
Q.火災保険をコストカットする方法は?
A.住宅性能を高めることで、保険料を大きく削減できます。
・省令準耐火構造
省令準耐火構造にすると、鉄骨造と同じ「T構造」認定を受け、火災保険料が約半額になります。
よくある勘違いとして、「準防火地域だから、窓や玄関扉を耐火仕様にすれば保険が安くなる」というものがありますが、準防火仕様にしても火災保険は安くなりません。ここは間違いやすいポイントなので注意してください。
・耐震等級3
耐震等級を取得すると、地震保険の保険料が割引されます。
耐震等級3 … 50%割引
耐震等級2 … 30%割引
耐震等級1 … 10%割引
保険料を安くすること自体が耐震等級取得の目的ではありませんが、住宅の安全性を高めるうえでも許容応力度計算による耐震等級3取得がおすすめです。

火災保険は「保険料を安くしたい」という気持ちから削りすぎると、万一の際にかえって大きな出費を招くことがあります。特に、火災・風災・家財補償など生活再建に直結する部分は、外してしまうと被害後に自己負担が数百万円単位になることもめずらしくありません。
反対に、ハザードマップでリスクが極めて低い災害や、生活スタイルに合わない補償は削っても問題ない場合があります。大切なのは「根拠を持って選ぶこと」。保険料の節約と安心のバランスを意識し、自分の暮らしに合った補償内容を組み立てましょう。
なお、火災保険とセットで検討されることが多いのが「地震保険」。
次回は、地震保険は本当に必要なのか、それとも不要なのか、メリットと注意点をお届けします。