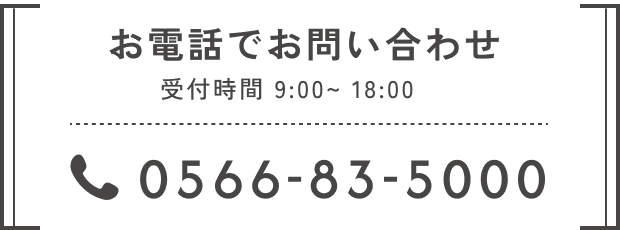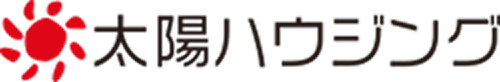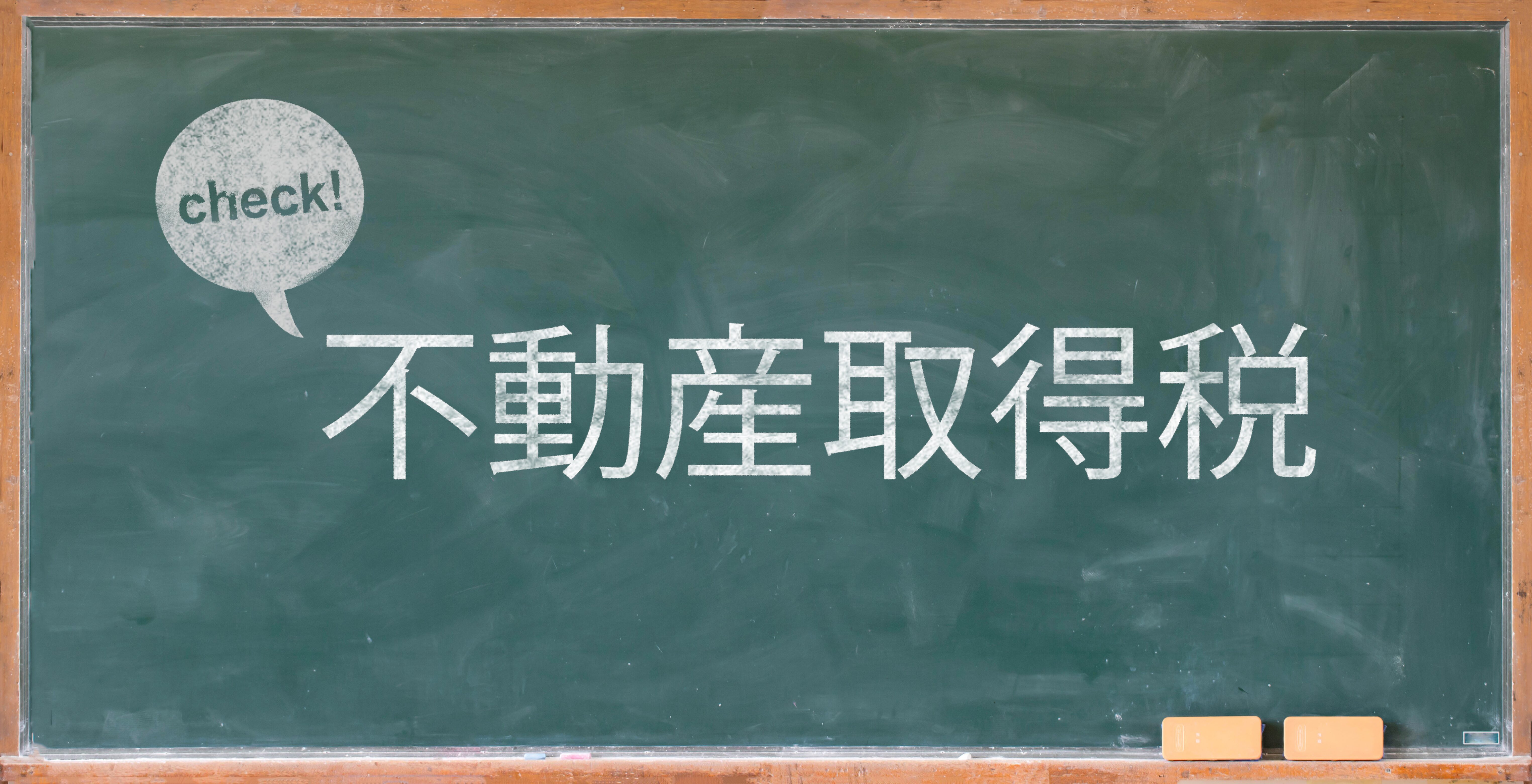COLUMN
家づくりコラム
【住宅ローン控除があってもふるさと納税はできる?】損をしない上限額の確認方法とは?
こんにちは、太陽ハウジングです。
「ふるさと納税をやってみたいけど、来年から住宅ローン控除が始まるし…本当にお得になるのかな?」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
どちらも“節税”の代表的な制度ですが、仕組みを正しく理解していないと「寄附したのに控除しきれず、自己負担が増えてしまった!」というケースもあります。
さらに、「住宅ローンを組んでふるさと納税をすると損をする」と耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
実際、住宅ローン控除によって所得税や住民税が大きく減るため、ふるさと納税で控除を受けられる税金の余地が少なくなるケースはあります。

でも、必ず損をするという意味ではありません。
あくまで仕組みを知らずに寄附額を決めてしまった場合に起こりやすいだけのこと。正しくシミュレーションをすれば、住宅ローン控除を受けながらふるさと納税もお得に楽しむことは十分可能です。
今回のコラムでは、住宅ローン控除とふるさと納税を組み合わせる際の注意点を、失敗例と成功例を交えて分かりやすく解説します。
■住宅ローン控除とは?仕組みと計算方法をおさらい
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、マイホームを購入した方が利用できる代表的な税制優遇制度です。住宅ローンを組んで住宅を取得または新築した場合、支払う税金の一部が一定期間控除される仕組みになっています。
・控除額は 年末ローン残高 × 0.7%
・控除期間は原則13年間
・控除は、まず所得税から差し引き、余った分は住民税から最大9万7,500円まで控除
例えば、年末残高が3,000万円の場合は控除額が21万円。
この21万円が、その年の所得税や翌年の住民税から差し引かれる仕組みです。
つまり、住宅ローン控除は「年末ローン残高に比例して税金を減らせる制度」ですが、実際には所得税と住民税の合計額が上限になるため、思ったより控除しきれないケースもあるのです。
■ふるさと納税とは?実質2,000円で返礼品がもらえる仕組みについて
ふるさと納税は、自分が応援したい自治体に寄附をすると、そのお礼として特産品などの返礼品がもらえ、さらに寄附金額の一部が税金から控除される制度です。
「実質2,000円の自己負担で楽しめる」と言われるのは、寄附額から2,000円を差し引いた残りが、所得税と住民税から控除される仕組みだからです。
・控除の流れは次のようになります。
1.所得税の控除(還付)
寄附をした年の所得税から一部が控除されます。確定申告を行えば、還付金として戻ってきます。控除されるのは「寄附額-2,000円」のうち、所得税率に応じた金額です。
2.住民税の控除(基本分+特例分)
所得税で控除しきれなかった分は、翌年6月以降の住民税から差し引かれます。
・基本分:寄附額に応じて一律10%程度が控除される部分
・特例分:住民税の所得割額の20%を上限に控除される部分
この「特例分」があることで、寄附額が大きくても最終的な自己負担が2,000円で済む仕組みになっています。
ここで注意したいのが、住宅ローン控除との関係です。
住宅ローン控除は、年末時点のローン残高に応じて所得税(+住民税の一部)が控除される制度です。つまり、ふるさと納税と同じ所得税と住民税の「税金の枠」を使って控除を受けます。
・住宅ローン控除で所得税がゼロになると、ふるさと納税の還付が受けられない
・住民税も控除で減っていれば、ふるさと納税の控除枠も小さくなる
結果として「思ったほどお得にならなかった」というケースにつながるのです。
【ポイント】
・住宅ローン控除の初年度は確定申告必須(ワンストップ特例は使えません)
・それ以外の年は、確定申告またはワンストップ特例制度で控除申請が可能
・控除できる金額の上限は、収入・家族構成・住宅ローン控除の有無などによって変わる
・所得税や住民税の負担が小さい人は、控除しきれず自己負担が2,000円以上になることも
【具体例】
寄附額10万円の場合
・自己負担:2,000円
・控除対象:98,000円(10万円-2,000円)
所得税から数千円が還付
住民税から残りの金額が控除
結果、トータルで98,000円分が控除され、実質2,000円の負担で済みます。
まとめ
・ふるさと納税は「寄附額-2,000円」が控除される制度
・控除は「所得税+住民税」から差し引かれる
・上限額は人によって異なり、税金の余地がある場合のみ“実質2,000円”になる
・手続き方法は確定申告かワンストップ特例制度(ローン控除初年度は必ず確定申告が必要)
つまり、ふるさと納税が“お得”になるのは、控除できる税金の余地がある場合に限られます。

■失敗例
住宅ローン控除とふるさと納税の失敗例|控除を受けられず損するケース
Aさん(会社員・40歳/今年マイホーム購入)
「返礼品で美味しいものを楽しみたい!」と、年末に10万円分のふるさと納税をしました。
ところが、Aさんは今年から住宅ローン控除が始まっており、所得税はすでにゼロ。さらに、住民税も住宅ローン控除で差し引かれていたため、ふるさと納税で使える控除枠がほとんど残っていませんでした。
その結果、寄附金10万円のうち控除を受けられたのは一部だけ。本来なら実質2,000円で済むはずが、自己負担が数万円に膨らんでしまった。
⇒「住宅ローン控除で税金がすでに減っている=ふるさと納税に使える枠も減る」この仕組みを知らなかったことが、失敗の原因と考えられます。
■成功例
住宅ローン控除とふるさと納税の成功例|上手に併用してお得に
Bさん(会社員・45歳/住宅ローン控除2年目)
毎年ふるさと納税を楽しんでいます。
事前にシミュレーションで確認したところ、住宅ローン控除を受けても住民税に余地があり、約5万円までなら実質2,000円で寄附できると分かりました。
そこでBさんは、家族の好みに合わせてお米やお肉を中心に5万円分を寄附。控除はしっかり適用され、翌年の住民税から差し引かれることに。
結果、食費の節約にもつながり、返礼品も楽しめて大満足。無理のない範囲でふるさと納税を活用できました。

■住宅ローン控除とふるさと納税を併用できる?上限額を確認する4ステップ
住宅ローン控除とふるさと納税を両立させるには、まずはご自身の税金の状況をきちんと確認することが大切です。
以下の4つのステップで順番に確認してみましょう。
① 源泉徴収票の「所得税額」を確認
まずは勤務先から年末にもらう源泉徴収票を手に取りましょう。
源泉徴収票には「所得税額(源泉徴収税額)」が記載されています。
もしこの金額が 住宅ローン控除額より少ない場合、所得税はすべて住宅ローン控除で消えてゼロになります。
所得税がゼロになると、ふるさと納税の「所得税からの還付分」は受けられません。
【ポイント】
「自分の所得税がいくらあるのか」をまず確認することが大前提です。
② 住宅ローン控除額を計算
次に、実際に住宅ローン控除額を計算します。
計算式は「年末のローン残高 × 0.7%」です。
控除できるのは「所得税+住民税の一部」まで。
所得税で控除しきれない分は、翌年の住民税から 最大13万6,500円まで控除されます。
計算例として、
年末残高が3,000万円の場合 → 控除額は21万円。
仮に、所得税が12万円なら所得税はゼロになり、残り9万円が住民税から差し引かれます。
【ポイント】
住宅ローン控除は「計算上の控除額」と「実際に控除される額」が異なる場合があります。実際に払っている税金以上は控除されないため、高額な住宅ローンがあっても税金がゼロに近い方は、ふるさと納税に使える枠も小さくなります。
③ 住民税額の見込みを確認
ふるさと納税は、所得税と住民税から控除される制度です。
そのため、住民税にどれだけ余地が残っているかも確認しましょう。
毎年6月頃に届く 「住民税決定通知書」 に、住民税の金額が記載されています。
会社員の方なら、給与明細に毎月天引きされる住民税額を見れば概算が分かります。
【ポイント】
住宅ローン控除が住民税まで食いつぶしてしまうと、ふるさと納税の控除枠は小さくなります。
④ ふるさと納税シミュレーションを利用
ここまで確認できたら、最後はシミュレーションで正確な上限額を調べます。
おすすめのシミュレーションサイトをご紹介します。
・ふるさとチョイス 控除上限額シミュレーション
https://www.furusato-tax.jp/about/simulation
・ふるなび 詳しく!本格シミュレーション
ttps://furunavi.jp/deduction.aspx#deduction_cat1
これらのサイトには 「住宅ローン控除あり」 を考慮した入力項目があります。
給与収入・扶養家族・住宅ローン控除額などを入力すれば、寄附できる上限額の目安が分かります。
【ポイント】
寄附前に「今年はどこまで大丈夫か?」を確認しておくことで、ふるさと納税のやりすぎによる損失を防げます。
こうして手元の書類とシミュレーションを組み合わせて確認することで、「ふるさと納税をしすぎて損をする」という失敗を防ぎ、本当にお得に制度を活用できるようになります。

「住宅ローン控除があるからふるさと納税は損をする」と考える必要はありません。
ポイントは、控除の仕組みを理解して、寄附できる上限額をきちんと確認すること。
そうすれば、住宅ローン控除とふるさと納税をどちらも最大限に活用できるはずです。
返礼品で暮らしを楽しみながら、賢い節税を実践してみてください。
「住宅ローン控除」「ふるさと納税」はどちらも家計にメリットのある制度ですが、その恩恵をしっかり受けるためには、ご自身の収入やローン状況、税金の枠を正しく把握することが大切です。
「自分の場合はどこまで控除できるのか知りたい」「無理なく、でも賢く制度を使いたい」
そう感じたら、ぜひ家づくり相談会やモデルハウスへお越しください。
太陽ハウジングでは、最新の税制を踏まえながら、お客さま一人ひとりに合った資金計画やスケジュールをご提案しています。
制度のしくみから具体的なシミュレーションまで、安心して家づくりが進められるよう、丁寧にサポートいたします。
▼家づくり相談会・建物見学会はこちら
イベント情報を見る