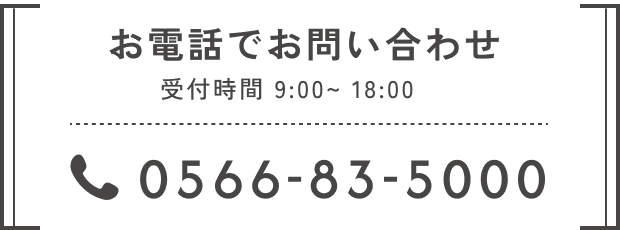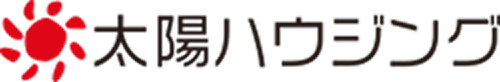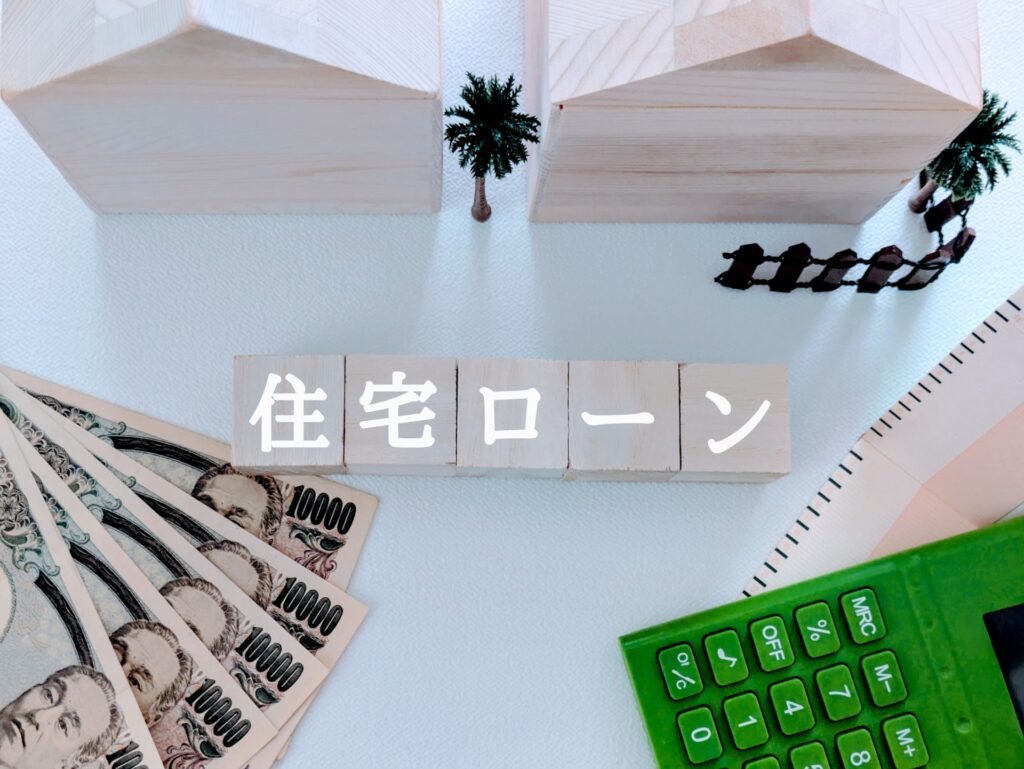COLUMN
家づくりコラム
【色がついている=危ないとは限らない!?】ハザードマップの正しい見方と賢い土地選びとは?
こんにちは、太陽ハウジングです。
今回は、これから家づくりをお考えの方にも、すでに西三河エリアで暮らしている方にも、
ぜひ一度立ち止まって知っていただきたい「ハザードマップ」の見方と活用法についてお話しします。
「うちはもう住んでしまっているから、今さら…」
「まだ土地も決まっていないから、災害のことはあとで考えよう」
そんなふうに思っていませんか?
でも実際には、もしもの時に命を守れるかどうかは、「日ごろの備え」と「正しい情報を知っているか」にかかっています。

■ハザードマップとは?
家族の「もしも」に備えるための、命を守る大切な地図。
皆さんは「ハザードマップ」を、きちんと見たことはありますか?
名前は聞いたことがあるけれど、実際に中身を見たことがない、という方も多いかもしれません。
でも、大切なご家族の命を守るために、今こそ一度じっくり見ていただきたい。
ハザードマップは、ただの「地図」ではありません。災害時にどう動けばいいかを考えるための「命を守る地図」になります。
■ハザードマップの役割
ハザードマップとは、簡単に言うと、
「その地域にどんな災害リスクがあるのか」
「どこへ避難すればいいのか」
「どのルートが安全なのか」を地図上でわかりやすく可視化したものです。
対象となる災害は多岐にわたり、たとえば以下のようなものがあります:
・洪水(川の氾濫による水害)
・内水氾濫(排水しきれずに住宅地側へ浸水)
・土砂災害(がけ崩れ・土石流・地すべり)
・津波・高潮(沿岸部の急激な浸水)
・地震(揺れやすさ、液状化、火災延焼など)
・道路の通行規制情報(災害時に通れなくなる道)
ハザードマップは、国土交通省や各市町村が作成・提供しており、小学校区などの細かな単位でも発行されています。最近では、「重ねるハザードマップ」や「わがまちハザードマップ」など、スマートフォンでも簡単に確認できるツールも整備されています。
2020年の宅建業法改正により、土地や住宅を購入する際には、水害ハザードマップを提示し、リスクを説明することが義務化されています。
しかし、契約直前の重要事項説明の段階で初めてハザードマップを見ても、「もう契約間近」という状態では冷静な判断ができません。 だからこそ、土地探しや家づくりの初期段階から、ハザードマップを確認しておくことが重要なのです。
■なぜ確認すべきなのか?
災害は、ある日突然やってきます。
天気予報のように「今週末は地震が来そうです」とは、誰にも教えてくれません。
「うちは川の近くだから、いつかは…」
「昔から住んでるけど、今まで一度もなかったから大丈夫」
そう思っていても、気候が変わり、災害の形も変わってきています。
ハザードマップを見ておけば、
・この道は災害時に通れなくなる
・この場所は2階まで水が来る可能性がある
・この崖の下は土砂災害警戒区域だった
というような、知らなければ逃げ遅れるかもしれない情報が手に入ります。
■住んでからも間に合う
「もう住んでしまっているし、今さら見ても仕方ない」
そんな声を聞くことがあります。
けれど、住んでいる今だからこそ、確認する意味があるんです。
例えば、小さなお子さまがいたり、高齢のご両親と暮らしていたりする場合、
「どこに逃げるか」
「どうやって避難するか」
日頃から災害時のことを話し合っておくことが、命を守る行動につながります。
実際に災害が起きてからでは、スマホもつながらず、地図も見られない可能性があります。だからこそ、スマホにダウンロードしたり事前にプリントして冷蔵庫などに貼っておく、避難所まで一度歩いてみる、などの行動が大切です。
■家づくりの「最初の一歩」でもある
これから新しく家を建てようとしている方には、ハザードマップは「土地選びの判断材料」としても欠かせません。
どれだけデザインが素敵な家でも、災害リスクの高い場所では不安がつきまといます。
しかし、逆に言えば――
「リスクを知ることで備えができる」
「リスクのある土地でも、家の工夫で安全性を高められる」
ということでもあります。
太陽ハウジングでは、土地選びの際にハザードマップを確認しながら、「どんな備えが必要か」「どんな家の建て方が安心か」を一緒に考えるお手伝いをしています。

■各災害リスクとハザードマップの見方
・洪水とは?
洪水とは、大雨によって河川が氾濫し、周囲の土地に水があふれる現象です。
西三河エリアでは「矢作川」「境川」「逢妻川」「猿渡川」など、流域が広い河川が多数存在し、豪雨による増水リスクが毎年のように指摘されています。
・ハザードマップで確認すべき「浸水深」
ハザードマップでは、洪水のリスクを「浸水深(しんすいしん)」という形で色分けされています。
| 浸水深 | 被害の目安 |
| 0~0.5m | 床下浸水(大人の膝くらい) |
| 0.5~1.0m | 床上浸水(腰程度) |
| 1.0~2.0m | 1階の軒先まで水没 |
| 2.0~5.0m | 2階の軒先まで水没 |
| 5.0m以上 | 2階の屋根以上が水没 |
2階建て住宅で「5mの浸水」が想定されている地域では、屋根の上が唯一の避難場所になる可能性もあり、大変危険です。
・見落とされがちな「内水氾濫」
「内水氾濫」とは、都市部などで排水が追いつかず、雨水が逆流して浸水してしまう現象です。西三河では、平坦地や造成地において排水能力を超えた豪雨時に被害が報告されています。
内水氾濫のリスクも洪水ハザードマップに反映されていることが多いため、「川からの距離」だけではなく「地形や排水状況」も確認することが重要です。
・土砂災害ハザードマップの確認ポイント
西三河エリアには丘陵地や斜面地も多く、とくに岡崎市、豊田市、額田郡などでは「土砂災害特別警戒区域」や「警戒区域」に指定されている地域があります。
【土砂災害の種類】
がけ崩れ:急斜面が崩れ落ちる
土石流:山の斜面から土砂と水が一気に流れ出す
地すべり:斜面全体がゆっくりずれていく
【ハザードマップ上の色分け】
黄色:警戒区域(住民への警戒が必要)
赤色:特別警戒区域(建築規制や避難勧告の対象)
特に土砂災害エリアは、長期優良住宅の認定が取れないなど住宅建築に影響が出る場合もあるため、事前に確認が必要です。
・津波、高潮のリスク
碧南市・高浜市・西尾市など、三河湾沿岸部では、南海トラフ地震などによる津波・高潮のリスクが想定されています。
津波浸水想定:海岸線から数キロ以内で、1〜5m以上の浸水が見込まれるエリアあり
高潮浸水想定:台風や暴風雨による海水の異常上昇による被害
高齢者や子育て世帯など、避難に時間がかかる場合は、事前に避難場所・避難経路を決めておくことが重要です。特に早めの避難計画が命を守る鍵になります。
・地震リスクと地盤の確認
日本は世界の中でも地震が非常に多い国。
そのなかでも、南海トラフ地震は、今後30年以内に70〜80%の確率で発生するとされています。
・地盤の揺れやすさマップ
西三河でも、埋立地や旧河川跡、田んぼを造成した土地などでは「揺れやすい」地盤である可能性が高いといわれています。
「地盤の強さ」「建物の耐震性能」「構造体の工法」の3つをバランスよく整えることで、地震に強い家が実現します。
・液状化現象とは?
液状化とは、砂地盤などが地震の強い揺れによって水を含んだ泥のようになり、建物が沈んだり傾いたり、上下水道・ガス・電気などのインフラが破損する現象です。
西三河地域も南海トラフ地震の影響を受けるエリアであり、地震の揺れやすさや液状化現象のリスクが高い地域も点在しています。
ハザードマップや地盤調査を活用し、地盤改良や免震構造の導入、基礎の補強などの対策が重要になります。住宅会社にしっかり確認を取りましょう。
・道路防災情報
災害時には道路が通行止めになることもあります。
西三河エリアでは、知多半島道路が通行規制区間となります。その他、落石の危険がある道路、橋の崩落リスク、冠水による通行止めの可能性なども表示されています。
避難経路を考える際は、実際に現地を歩いて確認し、通れなくなる可能性のある道がどこかを把握しておくことが大切です。

■ハザードマップを調べるには?
重ねるハザードマップ
公式サイト: https://disaportal.gsi.go.jp/maps/
洪水・土砂災害・津波・地震・道路防災情報などを重ねて確認できる国交省提供の便利なツールです。年代別の航空写真も閲覧可能で、土地の成り立ちまでチェックできます。
わがまちハザードマップ
公式サイト: https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/
市町村ごとに提供されている各種ハザードマップ(PDF)を検索・ダウンロードできます。印刷して手元に置いておくと、災害時にも安心です。
■命を守る行動は「知ること」から始まる
地震の発生件数は20世紀の約20倍に増加し、そのうち約2割が日本で発生しています。今や災害は「いつか」「どこか」ではなく、「誰にでも起こりうる日常のリスク」です。
災害が起きたとき、よくこう言われます。
「家なんてどうにでもなる。でも命は一つしかない」
本当にそのとおりだと思います。
ご家族とともに、安全に過ごすために。
これから家づくりを考えている方も、今すでにお住まいの方も、どうか「災害時に自分たちはどう動くのか?」を一度考える時間を持っていただけたらと思います。
このコラムをきっかけに、ハザードマップを見てみる。それだけで、命を守る第一歩になるかもしれません。
■色がついている土地は、本当にダメなの?
ハザードマップで色がついていると「危険=選んではいけない土地」と思いがちですが、本当にそうでしょうか?
たしかに、リスクを知ることは大切ですが、「そこは絶対にダメ」とも言い切れません。
色がついている土地には、実はメリットもあるんです。
・価格が抑えられている
人気エリアでも相場より割安な土地が見つかることがあります。
・日当たりや開放感がある
河川敷や低地は南向きで広々とした環境が多く、魅力的な立地も。
・整備された街並みや再開発エリアの可能性も
新しい街づくりが進んでいる場所も増えています。
一方で、デメリットも知っておいてください。
・将来的な資産価値(リセールバリュー)が下がる可能性
・火災保険の水災補償が必要になる場合がある(保険料が上がることも)
・実際に災害が起きた場合、被害のリスクがゼロではない
また、「色」だけでリスクを判断してしまうのはもったいないケースもあります。
例えば、同じハザードマップ上の色でも、現地に行くと微妙な高低差や地形の違いによってリスクが異なります。つまり、「掘り出し物の土地」が眠っている可能性もあるということです。
■大切なことは、リスクを知った上でどう備えるか——
大切なのは、「危ないからやめる」ではなく、リスクを知って備えられるかどうかです。
たとえば…
・高さのある基礎設計にする
・地盤改良を行う
・排水経路や避難経路を事前に確認する
・水災補償を含んだ火災保険に加入する
こうした備えをすることで、ハザードマップでリスクがある場所でも、安心して暮らせる家づくりが可能になります。

■太陽ハウジングでは、土地の選び方から一緒に考えます
太陽ハウジングでは、ハザードマップだけでなく、地形・地盤・過去の災害履歴・ライフラインの状況なども総合的に見て、安心できる土地をご提案しています。
また、災害リスクがあるエリアでも「安心して暮らすためのプランニング」をしっかりご提案します。
「ここに住んでも大丈夫だろうか?」
「ハザードマップで色がついていて不安…」
そんな時は、どうぞ私たちにご相談ください。プロの視点で、安心できる判断と対策をご提案します。
▼希望に合う土地が見つからない方へ
「気になる土地が見つからない…」「ネットで探してもピンとくる情報がない…」
そんなときは、太陽ハウジングの『土地リクエスト』をご活用ください。
ご希望のエリアや条件をもとに、スタッフが非公開情報を含めて土地をお探しします。

「気になる土地がある方」「ハザードマップを一緒に確認してほしい方」も大歓迎です。
また、太陽ハウジングの営業スタッフが【水害被害の土地のメリット・デメリットは?】を「家づくりQ&A」で回答しておりますので、気になる方はそちらもどうぞ。
▼家づくりQ&A 水害被害の土地のメリット・デメリットは?